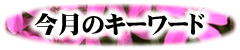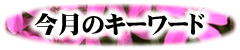[過去139〜154 回までの今月のキーワード]
トランプ政権、パリ協定「無視」の歴史的責任
2017/04/26(Wed) 文:(水)
トランプ政権による気候変動問題への対処方針がほぼ明らかになってきた。3月29日に示した大統領令の中の「エネルギー安全保障と経済成長の推進概要」によれば、気候変動問題に関連して次の事項が提示されている。▽各行政機関長は国内エネルギー資源の開発・使用の負荷になり得る全ての行政措置を見直し、そのためのプロセスを見直す ▽EPA長官は「クリーンパワープラン」見直しのために必要な措置を直ちに実施。これら考え方の通底は、2030年に向けた温室効果ガス・CO2の国別削減目標の設定と達成をルール化した「パリ協定」の否定であり、事前に指摘されていた「パリ協定の無視」の政策化、実質的なパリ協定の脱退化でもある。
これに対して、わが国は安倍晋三政権の是認姿勢や責任意識の希薄さによるマスコミ界の批判的意見の欠如が目立つ一方で、一部の環境NGOらが共同または単独で米国方針を指弾している。ちょうど、パリ協定で定める今世紀後半に向けた長期温暖化対策の取り組む方向を議論中なのに動きが少なすぎる。
気候変動問題が国境を超える人類不可避の地球環境問題として提起されてからほぼ半世紀たつ。この間、科学者は曲がり道しながらも数次の研究成果をあげ、科学的な因果関係の結論として温暖化の進行と脅威を注意・喚起→警鐘→警告→確証へと最高水準にまで高めた。延べ2000人以上が「対応策の実施と技術の適用に時間がない」との見解も強調してきた(5次にわたるIPCC報告書など)。後は、最も意識と行動が遅れている政治の世界だが、G7サミットはじめ十分な主導力が見えず、すでに30年以上も停滞して責任を果たしていない。しかし、今日の政治家の責任は30年前とは明らかにその度合いが大きく異なっている。一つは科学的材料の十分性、二つは今回明らかになったCO2許容総体排出量=残り1兆t、三つはこれまで起きた気候変動被害の大きさである。
こうしたことの理解の上で、国際社会がようやく実現したパリ協定を米国が「無視」の行動をとりこれに同調する国が増えれば、トランプ大統領には「温暖化を加速させた最悪の米大統領」として、水没した国や気候難民から裁判を提起されるかもしれない。気候変動問題では一日も早くトランプ氏だけではなく政治家が覚醒してもらいたいものだ。
次世代車の本命は燃料電池車だ
2017/04/05(Wed) 文:(徐)
トヨタ自動車が2014年末に世界で初めて燃料電池車(FCV)を発売、ホンダは16年8月から販売を始めた。FCバスはトヨタが今年、販売を開始した。FCVは水素社会へのスタートポイントであり、トヨタは第2世代車により20年には3万台販売を見込む。ホンダはGMと組み、20年に両社は第2世代FCVを世に出そうとしている。ドイツ・ダイムラー、BMW、韓国・現代自動車もFCVが実用化フェーズにある。自動車は120年の歴史の中で再び電動車の時代に戻りつつある。FCVにはエネルギーの多様化、ゼロエミッション化、走りの楽しさ、航続距離の長さ、水素充填時間の短さ、電源供給の大きさと、本命になる資格が整っているのだ。
FCVを最初に開発したのはGM。1964年に月着陸船・アポロに搭載したFCスタック(1.5kW)と同じスタックを32kWでトラックのバンに配置した。運転席以外はFCシステムがびっしりと詰まった、走る水素プラントだった。現在もGMに展示されている。トヨタは92年から、ホンダは80年代後半から開発を始めた。100年以上の歴史がある内燃機関とは全く異なる駆動機構のFCVが、1台700万円台と高価だが販売に入ったことは、開発スピードの速さを感じざるを得ない。
気候変動枠組み条約のパリ協定を踏まえ、世界が地球の平均気温上昇を2℃以下に抑えるには、50年にCO2を現状の90%削減が求められる。その実現には新車の90%が内燃機関でなくなることを意味する。
ハイブリッド車を現在まで1000万台を販売したトヨタにとっても、今後の本命はFCVなのである。同社は電気自動車(EV)の開発にも力を入れ始めたが、次世代車の核にFCVを置いていることに疑いはない。高い販売価格、少ない水素ステーションといった課題もあり、充電インフラが簡単なEVが本命になるとの声も聞かれる。日産自動車のEV「リーフ」は25万台を販売した。EVと家庭との電気の相互利用など利用価値も広がろうとしている。ただ再生可能エネルギーが普及し、再エネ電気の大量貯蔵、消費が30年には一般的になってくる。それは水素の時代であり、究極のエコカーともなるFCVとFCバス、FCトラックが持続可能なモビリティ社会を支える時代でもある。
小規模火力の新増設−エシカル消費も歯止めに
2017/03/22(Wed) 文:(一)
想定外への対処は難しい。とりわけ私権の制限につながったり、合法的な事業活動を制約したりするケースは厄介だ。環境負荷が大きい小規模火力発電の新増設計画に、どう歯止めをかけるのか−。環境省は「小規模火力発電等の望ましい自主的な環境アセスメント実務集」をまとめたが、実効性があるのかどうかは未知数だ。
出力11万2500kW未満の火力発電は環境影響評価法の対象外。6年前に起こった東日本大震災後の電力需給逼迫と電力自由化を背景に、主に石炭を燃料とする小規模火力発電計画が相次いだ。石炭火力は二酸化炭素(CO2)排出量が多く、小規模なほど効率を上げにくい。環境省は2014年度から有識者会議で検討を始めたが結局、事業者に自主的な環境アセスメントの実施を促す“手引き”に落ち着いた。
この間、地球温暖化対策として日本の温室効果ガス排出量を30年度までに13年度比26%減とする削減目標が決定。15年11〜12月に開かれた国連気候変動枠組み条約の第21回締約国会議(COP21)で地球温暖化対策の新たな国際枠組み「パリ協定」が採択され、日本の国際公約となった。
その前提とされた30年の望ましい電源構成(エネルギーミックス)では、石炭火力のウエートは「26%程度」。自家発電を含め、石炭火力発電の新増設が続けばその比率を上回る事態が想定され、目標達成が危ぶまれる。また、化石燃料からのダイベストメント(投融資撤退)は世界的な潮流となっており、環境NGOなどは小規模火力の環境アセス対象化と厳格な運用を強く求めていた。
検討開始の当初は事業化のハードルを上げる意図が強かった。だが、冷静に考えればアセスは適切な環境配慮を求めるのが趣旨であり、落ち着くべき所に落ち着いたともいえるだろう。
実務集を無視はできないにしても、従うかどうかは事業者次第。実際、検討作業を横目で見ながら、小規模石炭火力プロジェクトを強行するケースも散見される。
電力自由化で消費者は小売り事業者を選べるようになっている。エシカル消費(倫理的消費)が企業行動を左右できることを忘れずにいたい。
送電系統整備に発想を変えた高速道路活用を!
2017/03/07(Tue) 文:(水)
今や日本のほぼ隅々まで完成しつつある高速道路に、再生可能エネルギーを最大限活用できるように基幹送電連系線を全国津々浦々に張り巡らす「電力スーパーハイウェイ構想」が提唱されている。数年前から中堅のゼネコン会社が遠慮気味に提示、自らも先駆的な洋上風力事業を手掛け、過疎化が進む地方で地域活性化の有力な潜在的エネルギー資源を持ちながらそれが電力消費地の都市部と経済的な厚みにつながっておらず、いつも足踏みしている無念さをこの構想に結び付けた。
送電線建設のコストには電圧の高い電気を双方向で送れるよう送電線ケーブル、支持構造体(架設・管渠)、変電設備、基礎、建屋などのイニシャルコストと、稼働した後の点検、整備、定期交換などのランニングコストがかかる。北海道北部・東部地域や青森県、秋田県、岩手県などに集中する風力発電の電気を消費地に送るため、新たな施設整備や増強費用に1000億円以上の投資コストがかかり、国によるファンド出資と風力事業者による共同負担が現在具体化しつつある。しかしよく考えてみると、これらは投資回収に相当時間のかかる新規のインフラ投資だ。送電線建設・増強のために必要な用地を買収し、新たな鉄塔とともに数100km以上にわたって架空線を張り巡らす。割安だった風力のコストは電気料金の約1/3弱占めるといわれる託送料をさらに押し上げる結果をもたらす。
「電力スーパーハイウェイ構想」は、日本全国の高速道路を運用・管理する東日本・中日本・西日本・本州四国連絡橋の高速道路公団の高速道路に前出のインフラ投資対象設備を併設させ、道路の側壁等に高中圧の直流ケーブルを敷設。その投資コストは国の主導で行い、ランニングコストは送電系統を利用する利用者負担にするという。その原資はエネルギー特別会計の電源特会から現在支出されている年間計約1200億円の原子力立地協力交付金(未稼働の原発が多く実態がない状況)などを充てれば足りて、従来の増強費用見込みと同程度ででき、技術的にも容易と想定されている。また、高速道路公団は将来的な自動車利用の落ち込みにより収益が悪化する見通しで、新たな事業を付加することによって公団自身に経常的な収益効果をもたらし、ひいては高速道路を利用する国民にも裨益をもたらす。こうした事業改革を阻んでいるのは省庁の縦割り主義と電力会社の消極姿勢だという。
石炭火力CCSはゼロエミの対策費
2017/02/21(Tue) 文:(徐)
石炭火力は超臨界微粉炭燃焼でも天然ガス火力と比べほぼ2倍のCO2を排出する。世界で石炭火力は中国、インドを筆頭に今後も主力電源であり続ける。米国トランプ政権は気候変動政策を消し去り、石炭火力の復権と規制緩和・撤廃による石油パイプラインの新増設支援を打ち出した。カナダオイルサンド、米国シェールオイルの供給強化が動き出そうとしている。
そして日本は原子力発電が動かない情勢下、石炭火力の新増設が首都圏だけで1300万kWが計画にあがる。今後の石炭火力には日本の高効率発電技術の海外移転とともにCCS(CO2の吸収・貯蔵・利用)をどうするかが真剣に問われよう。
環境省まとめの15年度の国内温室効果ガス排出量は13億2100万tと前年度3%減少した。この削減量2600万tのうち、原発が15年夏以降再稼働した3基で400万tと寄与率は15%に及び、原子力発電のCO2排出量削減効果の大きさを示している。ただ国のエネルギーミックスで30年に電力量の22%とした原発比率は実現不可能であり、最大でも10数%だろう。その代替としても再生可能エネルギー拡大へのバックアップ電源としても、世界最高効率の日本発石炭火力プラントの新規立地とグローバルに技術を移転していくことは日本の重要なエネルギー戦略であるだろう。
石炭火力はkWhあたりCO2発生量が世界平均の958gに対し、日本の平均は864gと最も少ない。東京電力が福島県で2基を建設中の世界初の石炭ガス化複合発電(IGCC=1基50万kW)では効率55%と、現在の超臨界圧火力の40%を大きく上回り30%のCO2削減効果がある。IGCCは開発から30年程を経て商用段階にきたが、今後、燃料電池も併設したIGFCなどでさらに高効率化していくと同時に、CO2排出量を抜本的に減らすにはCCSの導入は最終的な姿だ。
CCSはコストが大きな問題。地球環境産業技術研究機構によると日本の石炭火力にCCSを導入するとほぼ発電コストと同程度のコストがかかるという。またCCSはCO2を充填して何年地中で安定しているかの答えもないのが現状。ただし低炭素時代に向け原発ではなく石炭火力をベース電源に導入していくのにCCSは欠かせない。それは「CCSのコストを、電力全システムをゼロエミションとする総合対策費として考えていかなければいけないだろう」と、茅陽一理事長はCO2発生ゼロに向けたエネルギーシステム全体の中で解決すべき姿勢が重要と指摘している。
牛ふんで水素社会−燃料電池との組み合わせに有望性
2017/02/08(Wed) 文:(一)
多くの読者には釈迦に説法だろうが、バイオマスは生物がもたらす再生可能な有機資源だ。家畜排せつ物や食品廃棄物などの廃棄物系バイオマスは、まさに“捨てればゴミ、使えば資源”。林地残材や稲わら、もみ殻などの未利用バイオマスも、ほったらかしなら朽ち果てるのみだ。これら多種多様なバイオマスをエネルギー源として利用すれば、二酸化炭素(CO2)が大気中に戻るだけで地球温暖化は無縁。いわゆるカーボンニュートラルだ。化石燃料に代替することで、CO2排出量を削減できる。
自然環境に恵まれた日本は、全国各地に利活用できる有機資源が眠るバイオマス大国。再生可能エネルギーの本命といえるかもしれない。
そんなことを改めて感じさせてくれたのが1月下旬、環境省の委託事業で北海道鹿追町にオープンした「しかおい水素ファーム」。畜ふん由来のバイオガスから水素を製造して地域に供給する実証施設だ。
酪農王国として知られる北海道十勝地方の鹿追町は人口5500人余り。大雪山系の南麓に広大な牧草地が広がり、人口の4倍近い約2万頭もの牛が飼育されている。毎日、大量に発生する牛ふんは肥料になるが、そのまま農地や牧草地に散布すると風向きによっては市街地まで悪臭が漂い、夏場の観光誘客の障害にもなっていた。
こうした問題を解決するため2007年、町は家畜ふん尿をメタン発酵させるバイオガス施設を建設。バイオガスを発電に利用し、副産物で悪臭がほとんどしない発酵消化液を液体肥料として地元農家へ供給してきた。今回の委託事業ではそこからもう一歩進み、バイオガスを精製して水素を“電気の素”として蓄える設備を導入。燃料電池車や燃料電池フォークリフト、さらに高圧ガスボンベを連結した集合容器(カードル)に水素を詰めて運び、地域の公共施設などにある定置型燃料電池で使えるようにした。
家畜ふん尿由来の水素製造・貯蔵・輸送・利用まで一貫したサプライチェーンの実証は国内初の取り組み。化石燃料を一切使わない水素サプライチェーンの可能性を探る。
発電した電気を蓄えておくのは簡単ではないが、水素にしておけば燃料電池でいつでも電気に変換できる。燃料電池とバイオマスの組み合わせは有望だ。
「脱炭素化社会づくり元年」に遅れるな!
2017/01/19(Thu) 文:(水)
2017年の国際社会は、「化石燃料」に別れを告げる「脱炭素化社会づくり元年」になる可能性が大きく、それに向けた経済活動やビジネス展開が激しくなりそうだ。昨年11月、全ての国が地球の温暖化を食い止めるための国際的な枠組み「パリ協定」が発効、2020年以降の温室効果ガス(CO2等)を大幅に削減する具体的な措置を講じる必要がある。わが国はその削減目標として2030年に△26%(2013年度総排出量比)を決定しているものの高い目標とは言えず、ましてパリ協定が最終目標とする2050年以降に現状からの「△80%削減」では政府方針の腰がまだ定まっていない。かつての「環境先進国」としての面目は消え失せている状況がある。
一方で、日本を代表するシンクタンク・三菱総合研究所の小宮山宏理事長(元東大総長)は、「わが国は中長期目標とされたCO2等の80%削減を達成できる」と断言する(「エネルギーと環境」の1月5日号)。その根拠は概略、▽年平均1.6%減となっているエネルギー需要の減少と省エネ指向、▽買い替えるたびに顕著な自動車の低燃費化や建物・住宅等の高断熱化、▽太陽光発電など再生可能エネルギーの飛躍的増大、▽エネルギー多消費型産業の停滞、▽ものの飽和状態――などを指摘する。これら根拠は単なる推測ではなく、現象ごとのデータと過去のトレンドを研究者としてきっちり積み上げたものだ。
対して、検討中の経済産業省の審議会はこうした見方に否定的な見解が主流であり、拙速な対策強化は経済成長の足かせとなる、国内よりも海外でのCO2削減対策の具体化が効果的として、まずは革新的な技術開発に期待をつなぐ対策を打ち出そうとしている。安倍政権が最重点とするアベノミクス経済政策のブレーキにはしたくないとの配慮が読み取れる。しかし世界的な脱炭素化に向けたビジネスの潮流は急速であり太い。欧米や途上国での導入が加速度的に進む再生エネルギーから供給される電力価格は、化石燃料系発電を遥かに下回る水準までに達しているという。また国内では大手電力会社による石炭火力の新増設計画に伴う投資資金確保が困難になりつつあり、洋上風力発電計画への変更を検討しているところが相次いでいるようだ。時代の変化は早い。
本年も読みごたえのある雑誌を肝に銘じて頑張りますので、よろしくお願いいたします。
バイオマス発電の新たな輸入燃料問題
2016/12/19(Mon) 文:(K)
再生可能エネルギーによる電気の固定価格買取制度(FIT)におけるバイオマス発電の設備認定が390万kWあり、一般木材系を中心に原料予定量の合計は1365万tである。国内では到底賄いきれず、海外からチップ、ペレットとアブラヤシ核殻(PKS)の導入が始まっている。そして加えて食用パーム油を輸入し発電する事業も登場してきた。燃料バイオマスの輸入は何のためのFITなのか疑問なのに、食料と競合のバイオ燃料輸入が地球環境問題に対応した発電事業に貢献するとはとうてい思えない。発電規模を大きくして効率を上げ、燃料は海外から輸入するのでは化石燃料を輸入し、大型火力発電を動かす資本の流出と同じであり、まして食料と競合するようなバイオ燃料の輸入は多いに問題ありと言わざるを得ない。
昨年12月とこの10月、茨城県で1万5000kW、2万3000kWのバイオマス発電所(ディーゼル発電)が運開した。太陽光発電を進めていた企業が新たにバイオマス発電事業へ進出、燃料はほとんど輸入パーム油である。同社は「商社を通して調達している」と安定供給を指摘する。このほか和歌山県で11万kW(年間20万t程度のパーム油輸入)の計画も上がっている。
FITの買取価格は木質バイオマスが1kWh32円、24円、13円、PKSは農産物の収穫に伴って生じるバイオマスとして24円が適用される。パーム油は食用の農作物であり、生産するマレーシアとインドネシアでは森林減少や生物多様性問題などの環境問題を抱えているという。パーム油には現在、可能性基準もなく、何よりも食料と競合する恐れが十分なのだ。
液体バイオ燃料の供給で石油業界は17年に50万葦をブラジルなどから輸入しているが、食料との競合に十分配慮、ガソリン比で温室効果ガスGHG削減量50%以上である用件を満たすことを求めている。バイオジェット燃料向けなどにバイオ液体燃料を開発するハイテク日本企業の原料は草本系である。世界的に食料と競合する農作物原料のバイオ燃料は縮小傾向だ。
FIT制度でのパーム油発電だと20年間は供給し続けることになる。バイオマス産業社会ネットワークも指摘するように、パーム油は環境・社会面で多くの課題を抱える農作物であり、現在の制度的には利用可能だが、食用パーム油発電は持続可能性に反する、FIT対象にはなり得ない燃料と言わざるを得ない。国は17年度以降のFIT価格の見直しで、バイオマスに発電規模で出力2万kW以上に新区分を設け、売電価格を下げる検討に入った。FIT制度が火を付けたパーム油を含む輸入バイオマスについては適正な導入のあり方が問われる。
トランプ米次期大統領−経済人としての眼力に期待
2016/12/09(Fri) 文:(一)
想定外の事態――。世界が注目する米大統領選で、民主党オバマ現大統領の温暖化対策を真っ向否定してきた共和党トランプ候補が勝利した。二者択一の選挙で、これほど波紋を広げた“想定外”の結果はかつてない。折しも大統領選が行われた11月8日は、国連気候変動枠組み条約第22回締約国会議(COP22)の開幕翌日。オバマ大統領の意を受け、モロッコで会議に臨んでいた米政府代表団のショックは想像に難くない。
次期大統領に決まったトランプ氏は環太平洋経済連携協定(TPP)に加え、昨年のCOP21で採択された地球温暖化対策の新たな国際枠組み「パリ協定」からも脱退する意向を表明していた。選挙前には「気候変動はでっちあげ」、「気候変動枠組み条約事務局への資金拠出をやめる」などと過激な発言を連発。気候変動に懐疑的な共和党の中でも急先鋒だった。
有権者に「ストロング・アメリカ・アゲイン(再び強いアメリカを)」と訴えてきたトランプ氏は雇用拡大もにらみ、エネルギー自給率100%を目指している。オバマ氏の看板政策で事実上、石炭火力排除につながる発電所の二酸化炭素(CO2)排出規制強化策「クリーンパワープラン」は廃止が濃厚だ。米国の石炭産業は息を吹き返すことになる。
ただ、すでに米国が批准した国際条約であるパリ協定からの離脱は、内政とは次元が違う問題だ。同協定の規定により批准国は発効後3年間、脱退を通告することができず、通告が効力を発揮するのは1年後。トランプ政権が2期目に突入するかどうかは別として、1期目の4年間はほぼ締約国としての義務を負う。
パリ協定は各国の自主的な取り組みを前提にしており、中国に次ぐ温室効果ガスの排出大国である米トランプ次期政権の姿勢が大きく影響する。主要排出国として米オバマ政権と歩調を合わせ、批准の先陣を切った中国の動向も左右しかねない。だが、中国政府は選挙結果を受け「我々は自国で決めた目標に向かって温暖化対策を進めていく」と会見で表明。先進各国の首脳もこぞって自制を促し、トランプ氏は冷静に現実を見始めたようだ。
トランプ氏は経済人。脱炭素社会の実現をビジネスチャンスと捉える先進的な企業は米国にも多数ある。物事の本質を見抜く眼力に期待したい。
電力の拒否反応強く、低迷する原子力再編論議
2016/11/21(Mon) 文:(水)
経済産業省が最重点課題として進めてきた電力改革の仕上げ措置を検討するための第三者機関として「電力システム改革貫徹のための小委員会」が9月に設置され、集中的な審議を行っている。委員会の名称に、霞が関の世界では珍しい労働争議などで多用される「貫徹」という用語をわざわざ使ったところに政策当局者の危機感が表れている。
一連の電力システム改革は2020年を目途に現在の大手電力10社の一貫経営体制(発電・送電・小売りの各事業。東京電力を除く)を法的に分離。電力会社間および他のエネルギー企業との連携・統合・再編を促す「総合エネルギー企業化」が最終ゴールとみられている。
もう一つ、10月に経産省が経済界の重鎮を委員にして立ち上げた「東京電力改革1F問題委員会」がある。1Fとは福島第一原発を指し、2011年におきた事故対応として賠償等が現在進められているが、その費用は廃炉等を含めると優に10兆円を超えるとみられており、財務会計上それを負債として一括認識すれば東電はたちまち経営破綻に追い込まれる。このため東電の経営破綻を回避させ、同時に20年に向けた電力10社の提携・統合・再編の道筋をつけるのが、先の委員会のミッションとみられている。
特に原子力事業については、各社とも再稼働見通しが目算よりも遅れているのに加え、新規制基準対応のための多額な投資と廃炉費用、中長期的な原発縮小方針による組織・人員の余剰化などから、各社の原子力部門を統合して1〜2社体制にという経産省の考えもある。そのためにまず東電の原子力部門を中部電力や日本原子力発電などと提携、さらに全社的な統合に発展させ、場合によっては原子力のみならず10社全体の再編・統合を実現するというシナリオだ。しかし電力業界には拒否反応が強く、政策当局の意図が空回りしている状況にある。その理由としては、せっかく前に進みだした原発再稼働の手続きに余計な問題を抱えたくないとの思いのほか、東電と提携しても1Fの負の遺産対応リスクが大きいこと、仮に提携・統合したとしても、それによって収益増大を生み出すようなエンジン役を果たす材料が見当たらないなどがある。年末までに一定の方向性を示す予定の原子力再編論議の帰すうが見ものだ。
環境先進国のスタンスを貫け
2016/11/08(Tue) 文:(一)
7〜18日にモロッコ・マラケシュで、国連気候変動枠組み条約(UNFCCC)第22回締約国会議(COP22)が開かれる。昨年末のCOP21で採択された地球温暖化対策の新たな国際枠組み「パリ協定」は主要排出国の米中やインド、欧州連合(EU)が早々に批准したことで要件を満たして4日に発効、COP22で閣僚級会合が始まる15日から第1回締約国会議(CMA1)が行われる運びだ。日本は批准手続きが間に合わず、オブザーバー参加となる。
日本が出遅れた格好になってしまったことに対し、批判の声が上がっている。当初、EUが域内国の手続きを待って批准書を提出する方針だったため、発効は2017年以降とみられていた。今臨時国会中に承認手続きを済ませる方針だった日本政府にとって、想定外の急展開だった。
5月の伊勢志摩サミット(主要国首脳会議)では日本が議長国を務め、首脳宣言にパリ協定をレガシー(遺産)としたい米オバマ政権の意を汲んで「16年中の発効に向けて努力する」と掲げた。国際情勢の変化を読み誤り、環境先進国を標榜してきた日本の体面を損なうことになった事実は厳粛に受け止めなければならない。ただ、「日本に不利なルールがつくられる」といった批判は的外れだ。
パリ協定は現行の京都議定書(97年、COP3で採択)に代わる20年以降の法的枠組み。すべての国が自主的に温室効果ガスの排出削減目標を策定し、5年ごとに見直して取り組みを徹底するスキームで、検証や報告など具体的な運用方法の検討は先送りされていた。パリ協定に付随するCOP決定で、発効後にCMA1を開いてルールブックを採択する手はずだった。
各国の環境相や政府高官が集うCOP22を前にパリ協定が発効することになり、タイミングを合わせてCMA1開催が決まったが、COP決定に基づくルールづくりのための特別作業部会(APA)は5月に1回目の会合が開かれ、やはり各国が意見を述べ合っただけ。「現状においてCMA1で決められることはない」(環境省幹部)のが実態であり、18年まで中断という手続きが採られる見通しだ。
日本はこれまで通り、環境技術で世界に貢献するスタンスを貫けばいい。
石炭火力の存在価値
2016/10/26(Wed) 文:(駒)
地球温暖化対策の新国際ルール・パリ協定が11月4日に発効する。2050年に地球の平均温度を現状より2℃以下に抑える高い目標の達成に向け、30年を目指したCO2排出量削減策が始まる。化石燃料の中で利用時発生のCO2の量が最も多い石炭火力は、再生可能エネルギーの導入が活発なEU諸国ではフェーズアウトの動きが高まる。一方、アジア諸国は賦存量が300年はある石炭への依存は今後も大きく、インドは再エネと併せて石炭需要を拡充、やがて世界一の輸入国となる動きだ。発電効率が高く、CO2排出量を大きく減らす石炭ガス化複合発電(IGCC)を東京電力が福島の2ヵ所へ出力54万kWで20年完成に向け建設に入る。豪州に膨大に賦存する褐炭を原料に水素を製造・液化し日本へ供給するシステムが始まる。石炭は日本が技術リーダーとなりCO2排出量の小さい世界のエネルギー安定供給に貢献していく価値あるエネルギーとなるべきだ。
今後、先進国はCO2を50年に80%削減しないといけない。世界のエネルギーの82%、電源では68%を化石燃料に頼っている現状を、電力エネルギーでは化石燃料と再生可能エネルギーの比率を逆転することが求められ、天然ガスと石炭火力をどう位置付けていくのかが問われる。
石炭需要はアジアでは今後も毎年6%で伸長していくとみられる。日本は30年を見越したエネルギーロードマップで石炭を重要なベースロード電源と位置付け、電源の26%を石炭火力でカバーしようとしている。そのためにはCO2の排出量を大きく減らしていく道しかなく、それはIGCC、ガス化発電に燃料電池も一体化したIGFCの実用化といった石炭のガス化技術への移行でもある。ガス化は発電と化学原料化、水素燃料化といった燃料の転換でもある。福島に建設する三菱重工業が開発した空気吹きIGCCは世界の今後の石炭火力に大きなインパクトを与えるだろう。それでも石油火力並みに発生するCO2の完全除去にはCCS(CO2の回収・貯留)となるが、日本では実用化できる貯留層は非常に少ない。CO2タンカーで海外へ運び、貯留するなども検討対象だが、CCSは長い年月の地中貯留という見えないリスクを抱える。石炭火力新設にCCSありきではなく、ガス化システムの高効率化や水素転換と併せて、CO2による石油・ガス田の増進や化学製品への転換なども急がれる。
築地市場移転問題のあれこれ
2016/10/18(Tue) 文:(水)
「東京大改造」をキャッチフレーズに当選した小池百合子東京都知事が快調な滑り出しを見せている。先月28 日の初めての所信表明では、まだ真相が明らかになっていない移転予定の豊洲市場の盛り土未実施や東京五輪・パラリンピックでの施設整備と膨大になった開催経費の妥当性など、従来のしがらみにはとらわれない意欲的な取り組みを鮮明にした。
いわば都政改革という「小池劇場」の開幕ともいえるものだが、自らが都知事を長く務めた石原慎太郎氏にさえ「東京都庁はとにかく伏魔殿」と言わせた“妖怪”が徘徊する都庁という大組織に、突然落下傘部隊の如く飛び降り、知事就任後に間髪を入れず懸案課題に立ち向かっている実行力は多くの都民の期待に応えるものだろう。
何よりも感心したのはそうした落下傘的な新参者という自覚がしっかりしていたのか、就任早々14 人のサムライよろしく「都政改革本部特別顧問」( 参与・調査員含む) を任命。環境省の地球環境審議官を務めた小島敏郎氏をはじめ、大学教授や経済界の重鎮など多彩な顔触れを揃え、”伏魔殿”への切込み体制を整えた。
ただ、都政改革という名の「小池劇場」はまだ始まったばかりであり、都議会との長年のなれ合いの下で進められてきた「慣例」は一朝一夕に直るものではなく、都自身もたまった膿を出す覚悟が必要となる。その結果によって幕の引き方すなわち都民の評価をどこまで得られるかが決まってくる。特に気がかりなのは11 月7日に予定していた東京築地市場の豊洲移転を延期、当初計画では市場の建物地下全体を土壌汚染対策のため盛り土( 有害物質の封じ込め)をすることになっていたのが実施されず、虚偽の説明をしていた件だ。盛り土予定の地下4.5mの空間は何のために変更されたのか? 変更時期は2011 年前後とみられているが、この移転地域では東京ガスが事業主体となった「スマートエネルギーネットワーク構想」( 電力・熱導管・通信などのインフラ整備) も同じ時期に進められており、そのための地下空間利用案があったのかどうか。いずれにしても、日本一の市場といわれる築地の移転では食べ物を扱うことから安全・安心の環境づくりが最大限優先されるべきであり、このままでは風評被害が拡散して五輪で訪日する観光客おろか国内の取引業者も敬遠することになりかねない。
人工衛星「いぶき」の国際貢献に期待
2016/09/16(Fri) 文:(一)
環境省、国立環境研究所、宇宙航空研究開発機構が共同開発し、2009年に打ち上げた世界初の温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」。日本における人為起源の二酸化炭素(CO2)濃度を09年6月〜14年12月の観測値から推計し、統計に基づく排出インベントリのデータとほぼ一致することが確認された。昨年末の国連気候変動枠組条約(UNFCCC)第21回締約国会議(COP21)で採択された「パリ協定」の実効性を担保する有力な手法になる。国際社会に貢献する環境技術として活用されることを期待したい。
いぶきはCO2とメタンガスについて地上にある観測点の約100倍、約2万3000地点の大気中濃度を観測する。排出インベントリと大気輸送モデルを用いて人為起源CO2排出による濃度の時空間分布を推定し、いぶきの観測結果を人為起源による影響の有無で分類。人為起源CO2の影響を受けていると判断されたデータと、その周辺で影響を受けていないと判断されたデータの差の平均値を求め、森林火災やシミュレーションで推定した植物などの影響等を除去して人為起源CO2の濃度とする。
パリ協定では20年以降、先進国だけに温室効果ガス排出削減を義務づけた「京都議定書」に代わってすべての国が協調して地球温暖化対策に取り組む体制になる。歴史的な転換といえるが“全員参加”を最優先したため、採択された合意文書には拘束力のある数値目標はない。
京都議定書が各国に温室効果ガスの排出削減量を割り振ったトップダウン型だったのに対し、パリ協定は各国の意思に基づいて全体をまとめるボトムアップ型。各国に温室効果ガス削減の目標策定を義務付け、5年ごとに報告と対策の見直し、取り組みの徹底を求めている。その際に今回、いぶきの観測値から推計して有効性を確認した手法により、各国から公表されるCO2排出量を高精度に監視・検証することが可能になる。
政府は日本企業が持つ高度な省エネ技術を資金支援により相手国へ移転し、温室効果ガス削減分をクレジット化して日本が受け取る2国間の排出権取引制度「JCM」を推進しているが、依然として市場メカニズムの活用にアレルギー反応を示す途上国がある。“間接的”な国際貢献なら批判を受ける余地もない。
「認定取消し」という太陽光発電事業の近代化
2016/09/02(Fri) 文:(水)
来年4月から新たな固定価格買取制度(FIT法)が施行され、経済産業省から設備の認定を受けながらまだ未稼働の状況にある太陽光発電事業(PV)の「認定取消し」が続出することになる。取消し一番手の対象は、FIT制度が開始された2012〜13年度に認定を受けた未稼働のPV事業34万件だ。
当時の認定は制度発足時だったことからともかく再生エネの導入拡大を重視、事業の質や確実性よりも量的拡大が最優先され、一定利潤が保証された買取価格の優遇ともあいまって認定市申請が殺到した。事業実施の確度が低いいわば玉石混交の事業が認定されたわけで、事業化の目的も一部のメガソーラーを除けば遊休土地の活用を目的とした投機、地域の不動産業・建設会社・電気工事会社などの共同投資による利潤追求を最大限にした事業化が大半だった。事業での買取り期間が終了すれば、あとは我関せずというもの。換言すれば、エネルギー供給の担い手や地球温暖化対策のためのCO2削減という社会的な要請とは無関係な経済行為だったともいえそうだ。
最近、来年からの認定取消しが現実化することに歩調を合わせるように、認定未稼働事業の権利を利益の出る間に商品化、あるいは損失にならないうちに他の事業者に転売・譲渡する動きが目立っているという。そうした流れもあって、大手商社が銀行と組んでファンドをつくりそこが未稼働事業を買い取り、改めて事業化を図る動きが出てきた。しかし、これも規模の大きいメガワット級のプロジェクト買い取りが対象であり、住宅用PVなど中小規模の案件は対象にしていないようだ。そこで指摘されているのが一定額を国が出資して官民ファンドを組成、そこが認定取消し候補の案件を買い取って事業化を図るというアイデァだが、経産省の再生エネ関係者は否定的だ。
つまり一攫千金を狙った事業者にはそこまでする必要はなく市場の淘汰に委ねるべきというのが主たる理由であり、今回の制度改正で最大眼目とした“PV事業の近代化”にも逆行するとの認識がある。新たな制度では電力会社との系統接続契約締結や運転開始後も含む設備管理の適正化、事業実施の確実性などが認定要件となり、事業としての適切性や透明性が格段に求められ、エネルギーインフラ施設として不可欠な存在を目指す。その先にはPV利用の100年構想があり、今の化石燃料に代わる「基幹エネルギー」時代の到来を見据えている。
燃料が有限の木質バイオマス発電の真の姿は…
2016/08/17(Wed) 文:(駒)
バイオマス発電はFIT以降に完成した件数が144件の49万kWとなり、設備認定を受けた規模は木質系を中心に316万kWになっている。バイオマス発電が本格的に普及してきたとみられるが、“いや待てよ”である。
バイオマス発電がほかの再生可能エネルギー発電と異なるのは燃料バイオマスが有限であることだ。この課題をクリアし、適正価格で安定した量を長い間確保できるのだろうか。今後完成するバイオマスの大型発電所はほとんどがアブラヤシの核殻(PKS)などの輸入バイオマスがカバーしている。設備認定量に供給できる木質バイオマスの量確保は内外を合わせても極めて困難なのである。規模を追わず、電気と熱利用と一体化したバイオマス・コージェネレーションの実現が求める姿であるのだが…。
バイオマス発電は再生可能エネルギー発電の中で最もリスクが大きい!――こう言われるのはバイオマス資源を長い年月にわたり安定的に確保できるかどうかがカギになるからだ。
木質系は一般木材から間伐材などの未利用材があり、国土の60%が森林面積で占める日本はそのポテンシャルは大きい。だが、15年7月時点でFIT認定を受けたバイオマス発電への原料利用量は1365万t。これは日本の木材生産規模の半分以上にあたる。このため国内からの供給は一般木質221万t、未利用材393万tにとどまり、輸入ペレットとPKSで計851万tと国産材を上回るとみられてもいる。
間伐材などを25年に800万m3に増やすとする林野庁の目標は山の路網整備が遅れている日本ではとうてい無理だ。またPKSは東南アジアから15年に46万tを輸入するも、「日本へは2〜3年後、最大見積もって150万〜200万t」と関係者は指摘する。
真庭バイオマス発電(岡山県真庭市=1万kW)のように未利用材の集積場を構え、地元からの燃料を安定的に確保し、高収益を上げる事業もある。16年度からは輸入材や石炭混焼発電の数万kW級が完成してくる。化石燃料と同じように日本の木質バイオマスも輸入して発電規模を稼ぐことが、二酸化炭素(CO2)の排出削減を最大の目的にした再生可能エネルギー発電の健全な普及につながるのだろうか。
地産地消のバイオマス燃料で熱をつくり、余ったエネルギーで発電をする設備を地域のスマートネットワークでつなぐエネルギーシステムの構築こそが日本の木質バイオマス発電の姿だと思う。こうした規模を追わないバイオマス発電が主流となるべきだろう。
【これより古い今月のキーワード】 【今月のキーワード 最新版】