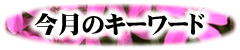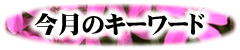[過去109~124 回までの今月のキーワード]
パリ協定-日本は環境技術で存在感を
2018/10/02(Tue) 文:(一)
12月にポーランドで開かれる国連気候変動枠組み条約第24回締約国会議(COP24)が迫り、2020年以降の地球温暖化対策の新たな国際枠組み「パリ協定」のルールづくりが佳境を迎えている。15年末のCOP21で採択されたパリ協定は、翌16年11月に1年足らずで発効した。準備作業が追いつかず2年後のCOP24までに、検証や報告などの詳細な運用ルールを策定することが決められていた。
パリ協定は先進国に温室効果ガス排出削減を義務づけた京都議定書に代わる国際条約。各国が自主的に温室効果ガスの排出削減目標を策定し、5年ごとに見直して取り組みを徹底するスキームで、平均気温の上昇を産業革命前に比べ2℃未満に抑えるため、温室効果ガスの排出量を今世紀後半に実質ゼロとする目標を掲げる。
だが、採択時から総論賛成・各論反対の色彩が強かった。途上国はルールづくりに際して資金支援の増額を担保する仕組みを求め、長年にわたり先進国が大量の温室効果ガスを排出し続け、気候変動による海面上昇(高潮)などで生じた損失・被害への補償問題もくすぶる。9月上旬に草案作成のため、タイで事務方による最後の準備会合が開かれたが両者間の溝は埋まらず、具体的な中身はCOP24での政治決着に委ねられた。
日本は国際協力で環境技術・制度を移転するだけでなく、途上国との協働により新市場創出とライフスタイルの変革をもたらす「コ・イノベーション」を標榜する。経済成長していく途上国の温室効果ガス排出量を、いかに抑えるかが脱炭素社会実現のカギを握るのは確か。日本にとって国際協力を新たな経済成長に結びつける機会にもなる。環境省はこれまで推進してきた地熱発電に加え、各国の状況に合わせて廃棄物発電や熱電併給システム、洋上風力発電などの再生可能エネルギーを中心としたインフラ投資拡大を挙げる。
昨年、パリ協定からの離脱を表明したトランプ米大統領のパフォーマンスは相変わらずだが、国際社会は平静を保っている。“地獄の沙汰もカネ次第”ということわざはあるが、日本は環境技術で世界に存在感を示したい。
わが国初の「ブラックアウト」発生
2018/09/21(Fri) 文:(水)
小説の世界だけかと思っていた「ブラックアウト」がわが国で初めて発生した。今月6日の北海道胆振地方を震源とする震度7の地震が引き金となって、大主力電源の北海道電力・苫東厚真火力発電所(出力計165万kW)がトリップ、道全域の295万戸が約1日半一斉停電となった。昭和20年代に現在の10大手電力会社体制になって以来、これだけ広域的に事前予告なしに大停電となったのは初めての経験だ。
「ブラックアウト」というタイトルの本が数年前に電力関係者の間で話題になったことがある。中身は某国の工作員がわが国に決定的な打撃を与えるため、柏崎刈羽原発近くの送電鉄塔によじ登ってダイナマイトで破壊、大停電を発生させて首都圏に経済的・社会的混乱をおこして、自らの目的を成就するという内容だった。
わが国は常々、電力の安定供給を最優先政策として掲げ、大停電の確率は欧米とは違って10年に一度位であり、それだけ電力供給の品質が高いネットワークが築かれている、と経済産業省は今日まで胸を張っていた。あの東日本大地震+福島第一原発事故においても、計画停電はされたが突然のブラックアウトはなかった。今回は想定外の地震が大規模発電所を直撃したとはいえ、本当に防げなかったのか十分な調査と検証が必要だ。そうでないと再度起こる可能性がある。
今回の大停電を起こした直接原因は、北海道の当時の需要ピーク約380万kWのほぼ半分を賄っていた苫東厚真が地震の衝撃でボイラー蒸気漏れや火災をおこしたことだが、唯一の主力電源がこんなにも脆いものなのか。きちっとしたメンテナンスをやっていたのかどうか。大手電力は近年の激しい電力間競争を勝ち抜くため、不要不急のコスト削減、特に送電系統設備や発電所機器のリニューアルなど修繕費の先送り措置が顕著になっている。欧米式の競争至上主義の導入が本来の公益事業という役割を毀損していないのかどうか。
もう一つは集中大規模電源供給方式の再検討である。これだけ大量の再生可能エネルギー導入が進んでいるにもかかわらずリスクの高い一点供給方式がとられ、分散型電源との機能分担が未だにできていないことだ。原発という大電源の扱いも含めて早急にあるべき姿の提示と議論が必要といえよう。
隔靴掻痒の気候変動適応対策
2018/09/03(Mon) 文:(水)
8月の後半だというのに全国的なこの夏の猛暑がまだ収まらない。1日の最高気温が40度を超えるような地域が出現し、「命の危険がある気象条件」という警告がテレビで何度も流された。
こうした地球温暖化が引き起こす気候変動対策への抜本的な対応策は国際政治の舞台や国内でも先送りされ、原因のCO2等排出を世界各国が自主的に削減する「パリ協定」が発効、年末にポーランドのカトヴィツェにて開かれる締約国会議(COP24)でその具体的な内容を決定しようとしている状況だ。つまり地球温暖化の進行→気候変動による被害の拡大に政治も行政も追いつけないという現実が我われの目前にあることになる。
「気候変動適応法」という法律が先の国会で成立、年内12月までに施行される。簡単に言えば、この法律は一定の地球温暖化の進行はもう止められないから、気温上昇が進んでも被害が最小になるように高温耐性品種の普及や亜熱帯・熱帯果樹への転換、防潮堤など公共インフラの再整備を計画的に進めるというものだ。ただ、道路・河川・ダムなどの公共インフラ事業と農漁業などを全く所管していな環境省主導の法律のためか、具体的な措置を見ると「気候リスク情報等の共有と提供を通じた理解と協力の促進」にトーンダウン、そのための情報システムと拠点づくりに化けている。これでは現に被害を受けつつある国民にとっては隔靴掻痒の感覚ではないか。
いま大事なことは三つのことに最重点で取り掛かるべきである。一つは、従来の公共事業が前提としていた安全指針等を総点検し、例えば30~50年に1回の稀有な気象条件に耐えるという設計・構造物でよいのかどうか。ダムの放水基準なども当然点検すべきであろう。二つは、その総点検結果を反映させた新たな公共事業政策を立案することだ。三つは、被害を被った住民らの保障や生活再建がどんな形で行われるのか、被害の受け損なのかそれをつまびらかに明らかにすべきだろう。こうした対応は何も公共事業分野に限ったことではない。停電も従来の想定をはるかに超えて頻発するかもしれない。西日本豪雨被害では保険会社の支払いが台風以外の水害では過去最高となって保険会社を慌てさせたという。気候変動の影響は過去の常識を根底から崩しつつある。
本当に間に合うのか、気候変動対策
2018/08/27(Mon) 文:(水)
この7月から8月にかけて日本も世界も記録的な猛暑が続いている。日本列島の最高気温は7月23日に埼玉県熊谷市で41.1度、8月6日に岐阜県下呂市で41.0度を記録するなど、歴代上位10の観測地点のうち実に4地点が今年の7~8月に集中、まさに猛暑というより「炎暑」という言葉がふさわしい気象異変だ。暑さだけではない。西日本一帯を襲った豪雨による大規模な土砂崩れやダムの決壊、河川の氾濫による多くの犠牲者と建物の損壊、欧米・中国でも記録的な高温や豪雨、山火事などが相次ぎ、まさに地球規模の異変が深刻化しつつあると言えよう。実はこうした地球規模の異変は、20年以上前からIPCC(国連気候変動政府間パネル)が指摘しており、この夏におきている気候変動事象の大半を的中させている。IPCCは地球平均気温の上昇による様々な悪影響だけではなく、局地的にその地域の地理的条件や気象特性によって今夏に頻発している極端な事象が発生すると警鐘を鳴らしていた。
2016年にはパリ協定が発効、現在2030年と50年に向けた温暖化ガス(CO2等)削減方策を検討中だが、およそ20年以上も前から指摘されていた世界のCO2排出量の削減は未だに実現せず増大トレンドは変わっていない。この間G7・G8やG20などで何度も議論され、対応策も打ち出されたが実効性は上がっておらず、政治の責任は依然として果たされないままだ。わが国でも8月3日、官邸主導による2050年以降のCO2等を80%削減するための戦略を検討する有識者懇談会が始まった。安倍首相肝いりの懇談会だが、議論のベースは環境対策を経済成長に取り込み成長なくして温暖化対策なしの前提という。
この前提は少しおかしくないだろうか。この10年を見ても経済成長率は微々たるものであり、そもそも成長率に大きく寄与する個人消費は今後伸びる余地が少ない。では経済成長が止まった場合、温暖化対策を停止するか緩めるという選択になるのか。そもそも50年目標というのも長すぎる。極論すれば、非現実的だが2049年に80%削減のための対策を一挙にとればそれでもパスという話だ。しかし気候変動被害は確実にいま拡大している。50年に向けた戦略よりも、目の前の20年や30年に向けたCO2等をどれだけ減らすべきかの検討こそ、責任ある政府の取り組む対応ではないだろうか。
ダイベストメントの潮流-再生エネを後押し
2018/07/26(Thu) 文:(一)
再生可能エネルギービジネス拡大の背景に、化石燃料からのダイベストメント(投融資撤退)がある。独立系の大手再生エネ事業者がまとめた資料によると、石炭・石油・ガスからの撤退を約束した世界の機関投資家は2017年末時点で900機関以上になり、その資産総額は実に約600兆円。4~5年前は地球環境問題の重要性に気づいた一部の機関投資家に限られていたが、ここ2~3年で一気に進展した。
半面でクリーンエネルギー、つまり再生エネ事業への投資が増え続けている。04年から17年の14年間で、累計投資額は約380兆円。ダイベストメントが世界的潮流になっていることを考えても、再生エネ投資は今後も高水準で推移していくだろう。
再生エネの普及とともに、発電コストも従来の電源と十分に競争できるレベルに低下した。国際再生可能エネルギー機関(IRENA)調べによる世界の均等化発電原価(LCOE)は、17年実績で太陽光が1kWh当たり10セント、陸上風力が同6セント。6年前の11年に比べ太陽光は18セント、陸上風力は2セント安となった。
こうした再生エネ電源単価の低下と供給量の拡大は、機関投資家にとどまらず社会経済全体を変える原動力になる。象徴的なのは再生エネ100%で事業運営を目指す国際的な企業連合「RE100」。17年時点の参加企業数は前年に比べ35社増えて122社。まだ日本企業は数えるほどだが、今年6月中旬には環境省が世界の公的機関として初めて、参加を決めたことで話題となった。
地域市場を独占してきた電力大手も、企業の社会的責任(CSR)の観点からダイベストメントの潮流には逆らえず、化石燃料を使う火力発電所の廃止や計画中止が相次ぐ。原子力発電所の再稼働や新増設も難しく、結果として再生エネ事業の展開に本腰を入れ始めている。
7月3日に閣議決定された政府のエネルギー基本計画では「再生可能エネルギーの主力電源化」が明記された。その一方で、15年に策定した30年度の望ましい電源構成比率(再生エネは22~24%)を踏襲したことを訝しむ声も。だが、社会が脱炭素社会実現に向けた好循環に入りつつあるのは間違いない。
再エネ電気はAIで賢く使い、人は創造的な仕事を?
2018/07/13(Fri) 文:(山)
6月下旬にパシフィコ横浜で第13回再生可能エネルギー世界展示会(再生可能エネルギー協議会主催)が開かれた。初日だったせいか、会場はあふれんばかりの人だかりというほどではなかったが、ほどほどの人出で、再生可能エネブームも一段落といったところかもしれない。おかげで、いくつかのブースで担当者の説明をじっくり聞くことができた。
特に東京電力の福島第一原子力発電所が過酷事故を起こした福島県は「原子力に依存しない、安全・安心で持続的に発展可能な社会」を目指し、そのために再生可能エネルギーの飛躍的な導入を進めている。同じブースの産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研究所とともに結構、人が集まっていた。
東電は福島第一だけでなく第二の4基の扱いについて「福島第一の廃炉とトータルで地域の安心に沿うものとするべく、第二も全号機を廃炉の方向」と6月16日に表明。福島県の原発10基はすべて姿を消すことになる。福島県は2040年までに県内で必要なエネルギーと同じ量を再生可能エネで生み出す「再生可能エネ先駆けの地を目指す」という目標達成を加速する。
企業ブースではパナソニックの「スマートHEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)」の説明に人が集まっていた。モノのインターネット(IoT)と人工知能(AI)を駆使して家電の運転制御、外出先からでも施錠の確認や風呂のお湯はり、室内の空気情報、機器の自動制御などで節電ができるという説明だった。
太陽光発電もAIが翌日の天気予報をチェックし、天気に応じて燃料電池(エネファーム)の沸き上げ量や蓄電池の充電量を調整する仕組みだ。再生可能エネに限らず、IoTやAIの活用は便利といえば、そのとおりだが、なんだか技術の進歩は人間の緊張感をなくしそうだ。雑事はIoTやAIに任せて人間はもっと創造的なことに力を注げということなのだろう。
もう一つ興味深かったのは中小企業や地域の仲間たちが手作りの自然エネルギー利用機器や省エネ機器を展示していたブースだ。小型太陽光パネルで充電できる空き瓶を利用した「ボトルスピーカー」や「ひょうたん型スピーカー」、太陽光を反射板で集光する湯沸かし器などのアイデアグッズに思わずほほが緩んでしまった。IoTやAIと無縁のこうした草の根の活動も再生可能エネ普及に欠かせないアイテムかもしれない。
エネルギー大競争時代-価格以外の「色」も忘れずに
2018/07/06(Fri) 文:(一)
2016年4月の電力小売り全面自由化に続き、17年4月には都市ガス小売りも全面自由化された。エネルギー産業は、まさに大競争時代を迎えている。電力自由化で異業種から参入した新電力(特定規模電気事業者)は、既存事業と組み合わせたサービスで電力会社(一般電気事業者)の切り崩しを図った。そしてガス自由化以降、予想された通り、エネルギー事業者間の熾烈な競争に突入しつつある。
思い起こしてみれば、通信事業も同じような道をたどった。85年の電電公社民営化(現NTTグループ)に伴う通信自由化で新電電が誕生。固定電話の中継サービスを足掛かりに携帯キャリアへと事業を展開した。そして情報通信社会といわれる今日、電電公社の流れをくむNTTドコモと並んで、一般消費者のコミュニケーションを担っている。
いわゆるモバイルコミュニケーション、移動体通信市場には外資の参入・撤退もあり、勢力図が固まったのはほんの10数年前。既得権益に守られてきた市場が段階的に解放され、技術革新を伴って収斂するまでには20年以上かかるのかもしれない。
地球環境問題も背景にエネルギー産業の将来像が見通せないなか、電力・ガス市場は専業から多角化を進める既存事業者、そして新規参入組が入り乱れる揺籃期にある。彼らにとってシェアの確保・獲得は至上命題。手っ取り早いアピール策として、安さを売りにするのが常道になる。契約期間を定めて料金を割引したり、電力・ガスのセット割販売など、多様な料金プラン設定もモバイル市場の揺籃期を彷彿させる。これから市場競争が本格化し、淘汰が進んでいくだろう。新電力幹部は「電力契約を切り替えた顧客層は価格に敏感。今後は流出を防ぐのが課題」とする。
ただ、通信とエネルギー産業では、事業環境に大きな違いがある。再生可能エネルギーの導入が進んできたとはいえ、依然として電力・ガスは原燃料の大部分を化石資源に依存し、事業そのものが地球温暖化をはじめとする環境問題に直結する。非化石価値取引などを利用し“環境に優しい”電力を売る事業者もあるがまだ少数派だ。
電力やガスは価格以外で“色がつけにくい商材”なのは確か。エシカル消費(倫理的消費)が企業行動を左右できることを忘れずにいたい。
後追いエネルギー基本計画を脱せよ
2018/06/28(Thu) 文:(水)
経済産業省が昨年から検討してきた「エネルギー基本計画」(第5次計画)の改定内容がほぼ固まった。政府部内調整を経て7月にも閣議決定される見通しだ。
第5次計画の特色は、国際的な温室効果ガス(CO2等)の長期的な削減を約束する昨年の「パリ協定」の発効を踏まえて、脱化石燃料≒低炭素社会づくりに向けたエネルギー需給構造の実現が国のエネルギー政策に最大限要求され、従来の2030年のみならず50年をも展望したシナリオを描いたことだ。しかし審議した委員会の有識者ヒアリングでは、「30年先の世界を予測すること自体が不可能。予測できないことを前提に近未来の課題を深く議論することが大事」(特に海外からの招聘者)などの意見が続出、議論のかみ合わない場面も多くみられた。
近未来である2030年の政策目標では現行と同様、エネルギーミックス(電源構成割合)の原子力=20~22%、再生エネ22~24%、火力56%の達成に引き続き努力するとして、改定計画では変更しない方針という。ところが現実は、こうした10年後に達成するとした目標とは大きな乖離が生じている。例えば、九州と四国エリアの電力需要に占める太陽光発電の供給割合がこの4月末から5月上旬にかけて80%を超える事態となり、系統維持のための再生エネへの出力制御措置が現実味を増している。日本全体の再生エネ30年目標の22~24%に対して、地方ではそれを遥かに上回る速さで進展している。
原子力を見てもミックスの目標達成は現実の進捗状況からいえばせいぜい10%というのが一部有識者の指摘であり、そうなる可能性も極めて高い。目標達成の蓋然性が極めて低い数値の継続は計画そのものの信頼性を失うばかりでなく、政策資源の投入(予算や制度の見直し、人材確保など)を誤り、後追い行政の典型となりかねない。原発は中長期的なCO2削減の手段としては不可欠だが、経産省が最も安いとする発電コストは福島第一原発事故関連費や安全対策費の急増、核燃サイクル費用の増大などからとっくに破綻している。再稼働に備えて確保している系統余力も現実的な見直しが必要であろう。経産省には3年ごとの計画見直し規定で修正すればよいとの見解もあるが、こうした後追い行政では世界の潮流から取り残され、エネルギー産業を弱体化させるだけである。
必至となるか中央省庁再々編の足音
2018/05/22(Tue) 文:(水)
財務省での公文書改ざんやセクハラ不祥事など一部官僚組織による国民の信頼を裏切る行為が相次ぎ、2001年以来の中央省庁再々編を検討する動きが強まっている。すでに自民党の行政改革推進本部(甘利明本部長)が役員会で現行体制・組織の課題洗い出しを確認したほか、5月以降新たな方向性に関する議論を行う方針だ。
現在の中央省庁は1府12省庁体制を基本として、これにその時々の重要課題を担務する兼務または専任の担当大臣を置く。当時の1府21省庁という大組織を、縦割り行政を排して政治主導による政策決定を目指すとして、強大な権限を持つ内閣府の新設や10以上の局を抱える総務省、厚生労働省の創設とともに組織のスリム化も図った。
そうした組織改編から20年近くたち、官僚組織の肥大化が目立つ一方で少子高齢化に伴う行政ニーズ、電子政府化の要請、地球温暖化対策の強化と再生可能エネルギーの主力電源化に伴う既存インフラの再構築など、現在の縦割り一府省完結主義では対処できなくなっている。加えて「森友学園」と「加計学園」の問題では、安倍首相への官僚による忖度が組織ぐるみで公文書改ざんという行為に発展、安倍政権の支持率低下を招いている。ここは人心一新、霞が関の再々編に打って出て国民の信頼を回復させ、安倍政権の延命につなげようという戦略であろう。ただ、膨大なエネルギーと政治力が必要となる“体力”が安倍政権に果たして残されているかどうかが微妙だ。
ではどのような霞が関の再編が望ましいか。財務省の分割再編や巷間指摘されている内閣人事局の見直しとか、単なる組織いじりにとどまってはならない。組織が必要となる前提にこそ目を向けるべきだ。例えば、①当たり前となっている単年度予算編成方式を2年ごとに変更、②一府省庁での政策展開完結主義の見直し(同じような行政組織の廃止)、③ほぼ無用となっている法律・制度の統廃合――など、大胆かつ繊細に次世代のニーズに対処できるようにすべきと思う。特に③は地味だが重要と思われ、現在ごまんとある法律のスクラップと廃止を具体化して、行政のスリム化と余力の確保に結び付けるべきではないか。
石炭火力の新増設-法的規制は避けたい
2018/05/11(Fri) 文:(一)
環境省が3月下旬に公表した2017年度の電気事業分野における地球温暖化対策進捗状況評価で、環境負荷が大きい石炭火力発電をめぐって課題や懸念を示した。同省は電力業界の自主的な温室効果ガス排出削減の取り組みを前提に、石炭火力の新増設を容認する姿勢だったが、ふたたび疑念を強めている。自主的な取り組みを徹底し、法的規制だけは避けたいところだ。
現状で国内の二酸化炭素(CO2)排出量のうち、電力部門が約4割を占めている。同部門の低炭素化が、温室効果ガス排出削減のカギを握るのは自明の理。だが、東日本大震災後の電力需給逼迫と電力自由化を背景に、安価な石炭を燃料とする火力発電計画が相次いだ。
15年に地球温暖化対策の新たな国際枠組み「パリ協定」が採択されたが、政府はそれに先立ち、日本の30年度における温室効果ガス排出量を13年度比で26%削減する目標を決めた。前提となる30年度の望ましい電源構成(エネルギーミックス)で石炭火力の割合は26%程度とされ、これに合わせて電気事業者35社は同年、30年度に販売電力量1kWh当たりのCO2排出量を示す排出係数0.37kg程度、火力発電所の新設に当たり実用化できる最良の技術(BAT)を活用することにより年間で最大約1100万tの排出削減という目標を設定している。
しかしながら、石炭火力の新増設計画は50件近くあり、計画どおり建設されると目標達成が危惧される。当時の望月義夫環境相は履行を担保する仕組みがないことから、環境影響評価法に基づいて事業者が提出した環境配慮書に対し意見書で「是認しがたい」を繰り返した。
こうした状況を受け、電力業界が自主的に取り組みをチェックする電気事業低炭素社会協議会(電力会社と新電力42社加盟)を設置し、翌16年に後任の丸川珠代環境相が経済産業省との間で新設容認の合意に至った経緯がある。ただ、同協議会は任意団体で拘束力を持たず、目標達成に向けた道筋を描き切れていないのが実態だ。
このままでは2年前の議論に逆戻りしてしまう。消費者が“環境に優しい”電力自由化のメリットを享受できるように願いたい。
河野外相のエネルギー政策への深謀遠慮
2018/04/06(Fri) 文:(水)
2月19日、河野太郎外務大臣に提出された「エネルギーに関する提言」の内容は、霞が関の官僚をざわつかせるのに十分だった。提言は「日本の新しいエネルギー・気候変動外交の方向性をまとめた」としているが、その矛先は経済産業省が検討中のエネルギー基本計画に向かったものだろう。提言の中身は、所掌する外交政策に対する課題指摘というよりも、従来の価値観にしがみつく国内のエネ政策に対する痛烈な批判となっている。
そのエキスを拾ってみると、▽各国はパリ協定が求める脱炭素社会の実現に邁進しているがその速度は日本を遥かに上回る、▽日本は再生エネの拡大で先行する諸国に水をあけられた、▽世界の努力と齟齬ある政策を続ければ、カーボンリスクを重視する世界市場でビジネス展開の足かせとなり、国際競争力を失う、▽エネルギーのことをエネルギーだけで考える時代は終わった――などなど。特に最後のフレーズは経産省への最大の当てこすりだろう。
提言を読んだ経産省の某課長は、「政府方針にフライイングしているどころか、所掌の枠を超えている」と、不快感を隠さなかった。世耕弘成経産相はエネ基見直しに関して、「2030年目標のエネルギーミックスの見直しは必要ない」と再三言明しており、河野外相が提言を踏まえたアクションを起こせば「閣内不統一」と批判され、政府内調整も難しくなる。また中川雅治環境相も、50年に向けた低炭素社会づくりへの礎として、石炭火力の削減と再生エネの主力電源化を提示、外務省―環境省の連合軍ができる可能性もある。
ただ外務省の有識者会合が河野大臣に提言した文書は、外交を進めるうえでのあくまで「参考」にするという位置づけで、それ自体が重要な役割を果たすものではない。形式的には河野大臣が提言を受けたとなっているが、しかしこの会合を河野外相自ら主導し数回出席するなど、この種の会合では異例ともいうべき力の入れようだった。当然、政治家として一時のパフォーマンスでは済まされない責任が今後も要求されよう。
「森友学園問題」で安倍長期政権が先行き不透明になってきた。河野外相が再生エネを主力にした日本再興と、封印していた脱原発を旗印に「ポスト安倍」に挑む姿が見られるのだろうか。
洋上風力は国が明確に各論を示すことから始まる
2018/03/22(Thu) 文:(徐)
日立製作所はベルギーの企業と共同で、台湾の電力会社から洋上風力発電21機の受注を内定した。日立が開発した5000kWダウンウインド型で初の大型受注となりそう。日本にとって今後の再生可能エネルギーのエースと見込まれる洋上風力は、世界で1880万kWに対し、日本は6万5000kW。日立が洋上風力の大型受注を最初に獲得するのは日本からではなく、国策の下400万kW洋上風力実現を目指す台湾からだ。日本が洋上風力で30年代に1000万kW以上を目指すには、国は港湾整備、国内部品企業の創出など産業育成につながる各論を示すことが不可欠だ。
海洋国家日本にとり、取り組むべき海洋エネルギーは海洋温度差発電、波力発電、潮流発電もあるが、いずれもマイナー。洋上風力こそ日本の再エネのエース格に育つ賦存量の大きなエネルギー源である。海外は欧州が北海中心に着床式の洋上風力を活発に導入、累計は英国の680万kWを筆頭にドイツの540万kWと続く。欧州は各国の強みを生かした事業の分業化(セントラル方式)を採用、太陽光発電(PV)で中国勢に市場を席巻された苦い経験を生かし、欧州企業の育成・強化を前面に押し出して臨む。英国の洋上風力は衰退する北海油田から代替する産業振興策でもある。欧州は10の拠点港を構え、単機風車の規模は1万kW以上を目指し、1億kW以上の導入に向け、北海に大規模送変電基地を造成する計画など中長期の明確な導入指針がある。
日本は現在、洋上風力の事業計画が270万kWほど上がってきてはいる。国も港湾に加え、一般海域も対象に共通ルールの策定に入る。日本も着床式がしばらくは中心になるが、まだ拠点港がなく、大型のSEP船(自己昇降式作業台船)もない。大型風車の部品メーカーも育ってない。洋上の動きが建設段階へ進まないのは、国の体系だった将来への導入指針がなく、事業の将来性がみえないからだ。
国は今後、全国5海域での重点ゾーニング選定などの検討に入ったが、一方で洋上風力は入札制にするなど導入前からいたずらに競争を強いるといったアンバランスな対応だ。投資額が大きい洋上風力は日本の産業育成につながる。欧州のようなはっきりとした導入拡大と産業振興の施策を明示した洋上風力のビジョンを示すべきである。浮体式の導入も念頭に置いて長期の具体的な指針を打ち出すことが洋上風力発電大幅拡大の道となる。
地域資源の竹を利活用-薩摩川内市の省エネに期待
2018/03/07(Wed) 文:(一)
地域の再生可能エネルギー発電所を活用する“地産地消型”の電力ビジネス、地域新電力が全国各地に誕生しているが、それに加えて、地域の特徴的な資源を省エネルギーに生かそうという取り組みもある。
鹿児島県薩摩川内市は2015年、豊富な竹資源をバイオマス燃料や高機能材料に生かすための産学官組織「薩摩川内市竹バイオマス産業都市協議会」を発足し、さまざまな利活用策を検討してきた。その一環として市内に工場を構える中越パルプ工業が竹を原料に、次世代のバイオマス素材として注目されるセルロースナノファイバー(CNF)を製造することに成功。用途開発につながるプロジェクトが同市を舞台に始動した。
集合住宅設計の日建ハウジングシステム(東京都文京区)は建材メーカーのLIXILと共同で昨秋、CNFを使った建材を開発して性能評価する事業に着手。樹脂窓や屋根、外壁などにCNF複合材料の適用を試み、既築の集合住宅に施工して断熱性や強度を比較検証する。環境省の委託業務「2017年度セルロースナノファイバー活用製品の性能評価事業」で採択を受け、2019年度末まで実施する計画だ。比較検証により効果を確かめるための集合住宅として、薩摩川内市が市営住宅の住戸を提供する。中越パルプも薩摩川内市竹バイオマス産業都市協議会の会員だ。
樹脂窓は樹脂サッシとガラスを組み合わせた建材。樹脂はアルミに比べ熱伝導率が約1000分の1で、断熱性能が圧倒的に高く、サッシメーカーは樹脂窓やアルミ枠と複合化した製品を開発している。熱変形しにくく高強度のCNF複合樹脂を適用してサッシの断面積を小さくし、複層ガラスと組み合わせることで断熱性能をさらに高め、同時にサッシの耐候性も向上させて長寿命化を図り、環境負荷低減につなげる狙いだ。屋根や外壁についてはCNF複合材料の吹き付けなど、さまざまな施工方法が検討されている。
CNFの用途として最も注目されるのは軽量・高強度を実現するゴムや樹脂との複合材料化。自動車部品や建材へ適用が期待されているが、未だ実用化には至っていない。地域活性化への思いが推進力となって、地方都市で世界に通じる省エネ技術が結実することを期待したい。
大手電力会社自らが再生エネの主役に
2018/02/28(Wed) 文:(水)
最近の再生可能エネルギーに関する系統制約問題や買取価格の引き下げ要請、火力発電の調整力活用などの議論を見ていると、経営資源が豊かで電気のプロでもある大手電力会社がなぜ再生エネ事業の主役にならなかったのかつくづく不思議に思う(子会社等が手掛けている例はあるが)。欧米では、従来の電力会社がいち早く再生エネ普及拡大の潮流を読んで自ら事業を積極的に展開しており、例えばフランスのEDF社は今後世界中でおよそ5000万kW規模(100万kW原子力発電の50基分に相当)の再生エネ事業を今後展開する方針という。
その理由はどうやら次のようなことらしい。一つは当初のFIT制度においては、電力小売りの全面自由化もあって大手電力が直接再生エネ事業者になるのを制度上認めず、異業種からの新規参入を促す政策に重点が置かれたこと。二つは、当初は再生エネコストが他の電源に比べて割高で、その国民負担に大手電力は批判的姿勢をとっていたこと。三つは原発の再稼働を最優先としたのに加え、火力燃料であるLNG・石炭の長期契約による引き取り義務があり、これをチャラにはできなかったこと。
では大手電力が自ら再生エネ事業を手掛けた場合のメリットは何か。系統制約問題では空き容量として確保している原発再稼働分や石炭・LNG新増設分の送電容量を自在に再生エネに活用できる可能性が高まる。再生エネ発電コストの引き下げには土地代や工事費等の削減が必須だが、十分に活用していない発電所用地などを潤沢に持つ大手電力がやりやすいはずだ。改正FIT法では再生エネ発電所の立地に対して、環境への配慮など事業の適切性を確保する措置が規定されたが、質の高い開発を確保する上でもプレーヤーの資質は重要なことと思われる。
そうした問題意識を強めて次世代再生エネ事業を開拓する意欲を示しているのが、自民党政調の組織である「再生可能エネルギー普及拡大委員会」(片山さつき委員長)が立ち上げた再生エネ利用拡大のためのタスクフォース(TF)だ。このTFはほぼ全国の電力供給エリアごとに設置され、当該地域出身の自民党議員に加えて地域の大手電力が参画し、系統制約の解決をはじめ電気事業に係わる料金引き下げなど地域の目線であらゆる問題を俎上にあげ、関係者間で解決の方策を模索するという。
石油ピークは意外に早く訪れる
2018/02/07(Wed) 文:(徐)
再生可能エネルギーの増加、天然ガスの拡大、自動車の電動化と多様なエネルギー時代を迎え、石油ピークが意外と早く訪れる可能性が高まっている。石油埋蔵量が30年と言われ続け、需要に供給が追いつかなくなるのがかつての石油ピーク説だった。シェール革命で石油、天然ガス生産世界一となった米国の存在が石油枯渇を消し去り、石油需要のピークが現実味を増してきた。
自動車の電動化への切り替えスピード次第だが、シェールガス、オイル増強もあって長期に石油価格は現状維持されそうであり、価格が石油ピークの時期を左右しそうだ。
石油は発電燃料として大量に利用されてきた。現在も各電力会社は非常用に石油火力を保有する。福島第一原発事故時の電力供給不足カバーのためフル回転したが、再エネ電源がシェアを高め、天然ガス火力の高効率化が進む今後の電源ミックスの中では消えていく電源である。石油需要の中心は自動車であり、今後、市場が電気自動車、プラグインハイブリッド、燃料電池車に移っていけば、石油需要はどんどん減っていく。
ハイブリッド車が普及し、内燃機関エンジン車の燃費向上もあってガソリンスタンドへのドライバーの頻度は減り、全国のガソリンスタンド数は3万4000軒とピーク時の40%減だ。今後、世界の新車のすべてがゼロエミッションビークル(ZEV)になるのを2050年と想定して、日本エネルギー経済研究所は「石油消費は30年頃にピークとなり、50年頃には16年頃と同等まで減少する」と仮定付きだがピークの可能性を示す。
IEAは17年にまとめた40年までのエネルギー見通しで、世界のエネルギーシステムはクリーンエネの急速普及とコストダウン、電化の進展、中国のクリーンエネへの移行、米国はシェールガス、タイトオイル輸出国へ、といった4大変化をバックに、石油は自動車消費の減少で20年代半ばまでは堅調な石油需要が、後半からは鈍化するとしている。ただし石化製品向けが堅調に伸び、40年までは増加傾向が維持されそうとみている。世界一の石油王国・サウジアラビアは世界最大の石化コンビナートを2兆2000億円をかけ25年に完成する。石油の今後の需要を象徴するプロジェクトだ。日本は30年に1次エネルギー構成比で石油は30%とトップに置いているが、国の「やる気」を前提に、電動車両がどこまでブレークするかによって構成比は下がる。
再生可能エネルギー立国に向け全力投球
2018/01/15(Mon) 文:(山)
新年あけましておめでとうございます。
旧年中は「創省蓄エネルギー時報」をご購読いただきましてありがとうございます。本年も創エネ、省エネ、蓄エネに関するニュースや解説に全力で取り組む所存でございます。引き続きのご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
さて、本年は江戸幕府が倒れ、明治政府が発足してから150年の節目に当たります。西洋文明が流れ込み〝文明開化〟が始まりました。その象徴の一つが電灯です。1882年に東京・銀座に電灯(アーク灯)が灯りました。1886年に東京電灯(東京電力の前身)が開業するなど、電力会社が各地に設立され、発電を開始しました。
当初は小規模の火力発電所が各地にありましたが、日本の電力は水力中心の「水主火従」でした。それが1960年代前半から「火主水従」に移行しました。1963年に茨城県東海村に動力試験炉が建設され、ここから原子力発電が始まりました。その後は火力、原子力、水力による電力供給が続いてきました。
1973年に第1次オイルショックが発生、政府は1974年にサンシャイン計画で再生可能エネルギー開発に乗り出しました。温室効果ガスの排出による地球温暖化が深刻化したことも再生可能エネルギー普及政策に拍車をかけました。さらに2011年3月の東日本大震災で福島第一原子力発電所が過酷事故を起こして原発が停止し、2012年7月に再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)を設けました。
弊誌は2010年10月に「時報PV+」として創刊、本号が154号になります。この間、再生可能エネルギーによる発電、省エネ、蓄電池、水素エネルギーの利用などの技術開発、普及に関する報道を続けてまいりました。ただし日本の再生可能エネルギー普及は諸外国に比べ、遅れているのが現状です。再生可能エネルギー装置・関連機器ビジネスでも海外の後塵を拝している部分もあります。
弊誌は今年も再エネ・省エネ・蓄エネの普及拡大、そしてそれらの関連産業の隆盛を目指し、全力で「創省蓄エネルギー」の報道に取り組んでまいります。
【これより古い今月のキーワード】 【今月のキーワード 最新版】