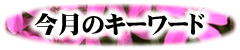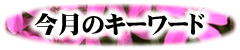[過去124~139 回までの今月のキーワード]
再生可能エネルギー立国に向け全力投球
2018/01/15(Mon) 文:(山)
新年あけましておめでとうございます。
旧年中は「創省蓄エネルギー時報」をご購読いただきましてありがとうございます。本年も創エネ、省エネ、蓄エネに関するニュースや解説に全力で取り組む所存でございます。引き続きのご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
さて、本年は江戸幕府が倒れ、明治政府が発足してから150年の節目に当たります。西洋文明が流れ込み〝文明開化〟が始まりました。その象徴の一つが電灯です。1882年に東京・銀座に電灯(アーク灯)が灯りました。1886年に東京電灯(東京電力の前身)が開業するなど、電力会社が各地に設立され、発電を開始しました。
当初は小規模の火力発電所が各地にありましたが、日本の電力は水力中心の「水主火従」でした。それが1960年代前半から「火主水従」に移行しました。1963年に茨城県東海村に動力試験炉が建設され、ここから原子力発電が始まりました。その後は火力、原子力、水力による電力供給が続いてきました。
1973年に第1次オイルショックが発生、政府は1974年にサンシャイン計画で再生可能エネルギー開発に乗り出しました。温室効果ガスの排出による地球温暖化が深刻化したことも再生可能エネルギー普及政策に拍車をかけました。さらに2011年3月の東日本大震災で福島第一原子力発電所が過酷事故を起こして原発が停止し、2012年7月に再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)を設けました。
弊誌は2010年10月に「時報PV+」として創刊、本号が154号になります。この間、再生可能エネルギーによる発電、省エネ、蓄電池、水素エネルギーの利用などの技術開発、普及に関する報道を続けてまいりました。ただし日本の再生可能エネルギー普及は諸外国に比べ、遅れているのが現状です。再生可能エネルギー装置・関連機器ビジネスでも海外の後塵を拝している部分もあります。
弊誌は今年も再エネ・省エネ・蓄エネの普及拡大、そしてそれらの関連産業の隆盛を目指し、全力で「創省蓄エネルギー」の報道に取り組んでまいります。
「たまには停電も」は愚かな発想か?
2017/12/25(Mon) 文:(水)
12月7日。自民党本部で「再生可能エネルギー普及拡大議員連盟」の会合が開かれ、全国的にネックとなっている電力会社の送電線に再生エネ電源をつなぐための新たな方策が熱心に議論された。講師役の有識者は、大きな焦点となっている東北北部4県の主要幹線の利用率を分析した結果、「実際の送電量は全体容量の20%以下に過ぎない。高速道路に例えるならば、中はガラガラにすいているのにゲートで多くの車両がまだかまだかと待っている状態だ」と指摘した。
しかし東北電力からすれば、送電系統の空き容量計算には▽万が一の設備トラブルと事故への対応(安定供給)、▽建設予定電源からの仮押さえ(先着優先)、▽系統に接続する(予定含む)全電源が同時に定格出力になることを前提――など、一定のルールで運用しているとなる。
ここでの問題は、送電系統でも絶対条件とされている「安定供給」の考え方だ。確かに気象条件に左右される太陽光発電や風力発電は、そのシステムにアクセルはあってもブレーキがないといわれ、系統につながれる電気は日中の負荷変動が激しい。このため、停電を起こさない「安定供給」の措置として、全ての電源が最大(定格)出力になる状態、送電系統のトラブルや自然災害などに備え、一定割合の空き容量確保が必要になるという。
これに対して、有識者は過去の潮流実績やトラブル発生の確率からみても、あまりにも過剰スペックの要求であってそのことが電力システムのコストを押し上げ、ひいては託送料金の高止まりとわが国の高い電気料金の要因になっていると強調する。欧州では10年に1回の大停電発生を予め組み込んでシステムを構築、過剰スペックを避けていると話す。
43年前、豆腐屋の作家と言われた松下竜一氏(故人)が「暗闇の思想」という本を書き、便利すぎる現代文明に警鐘を鳴らしたことがある。元来、分散型である再生エネの活用は最小限の需要を賄うための電源であり、ある程度の不安定さを社会全体で受け入れ、10年に1回程度の停電があってもよいのではないか。停電が起こった日はローソクを囲み、来るべき大災害への備えや日ごろ不足がちな家族団らんの日と決めて、電気という文明の利器に感謝するというのは愚かな発想だろうか。
「悪の枢軸」とまで言われた日本
2017/12/07(Thu) 文:(水)
11月18日に閉幕したドイツ・ボンの国連気候変動枠組み条約第23回締約国会議(COP23)で、環境NGOが表彰する特別化石賞に米国政府、化石賞には日本政府が昨年に続いて選ばれ、今回もかつての「環境立国日本」はその面影すらなかった。会場では「日本は悪の枢軸か」とまで批判され、ある参加者は顔色を失ったという。
これは民間企業人の話だが、国内で具体化中の約2000万kW規模の石炭火力新増設計画と東南アジアへの石炭火力輸出ビジネスが痛烈に批判されたものだ。海外から見れば、ようやく先進国対途上国の対立を乗り越えてパリ協定の詳細設計をつくるところまで漕ぎつけたのに、自分の国の利益のみを重視して今後40年も大量のCO2を排出し続ける石炭火力を新規につくるということを正気で考えているのか、ということになる。欧米でも既存の石炭火力の稼働は多いが、今はその比率をどうやって減らすか国を挙げて議論している最中なのに、ということもある。
今回のCOP23会議の前後では二人の国際的な賢人の発言が目を引いた。一人は国際移住機関のスウィング事務局長であり、「地球温暖化の進行に伴い海面上昇などから住んでいる場所を追われる“環境難民”が顕在化している」(18日付け毎日新聞)という指摘で、そうした地域としてアフリカ・サハラ砂漠の南縁とキリバスなど南太平洋の島国をあげていた。
もう一人はCOP23直前に来日した環境活動家のアル・ゴア米国元副大統領だ。「不都合な真実」パート2の日本上映に合わせて訪日したが、インタビューに答えた話が印象的だった。曰く、▽気候変動問題は20年前の京都議定書が採択された状況とは激変した(環境難民の発生などを指す)、▽安価なコストの風力や太陽光発電、蓄電池という具体的な解決策が出てきた――などを指摘し、あとはそれらを政治がどう選択するか、決して手遅れではないとも語った(18日付け朝日新聞)。
日本ではCOP23の直前に主要国の国会議員らが集まって議論する「地球環境議員連盟」(GIA)の総会が開催されたが、国際的な石炭火力への批判を恐れてか会議の中身や総括が一切公表されていない。COP23では「脱石炭に向けたグローバル連盟」が創設されたが日本は参加を保留している。「悪の枢軸」とまで言われた環境後進国を払拭できるか正念場である。
持続的な普及の時代に向かう太陽光発電
2017/11/22(Wed) 文:(駒)
経済産業省は再生可能ネルギーの導入量を牽引してきた太陽光発電(PV)の固定価格買取制度(FIT)の価格を2018年度にはさらに引き下げ、非住宅用を1kWh20円以下にする方針だ。FITが始まった12年度の同42円の半分以下になる。そもそも42円は世界でも例がない高すぎた売電価格である。それはPVに参入する事業者を増やし、安易な参入が今になって倒産に追い込まれる例も増えている。
高い買い取り価格はPV導入量を16年に累計で4000万kWと、FIT以前の66万kWから飛躍的に増やした。そして今後は日本のPV産業は欧米より割高な導入コストの一層の引き下げが望まれる。FIT価格が10円前後となり、さらにFIT制度がなくても自立していくだけの発電電力量が稼げる質の高いPVをグローバルに提供していく事業展開が望まれる。
国際エネルギー機関(IEA)が10月に報告した16年の世界の再生可能エネルギー導入量は記録ずくめだった。全体で1億6500万kW、特筆すべきはPVが前年比50%以上伸び、断トツの74000万kWと今までトップだった石炭火力を上回ったことだ。PVの国別では中国が3400万kWと圧倒した。「PVは世界で最も大きな電源となった。オークションでの電気落札額は3年で半減、インド、メキシコ、UAEでは1kWh3~4.5セントになり価格も大きく下がっている」と貞森恵祐エネルギー市場・安全保障局長はPVが世界一の電源になってきたと指摘する。
日本はFIT売電価格が下がり、2000kW以上では競争入札制導入が始まった。最初の入札の答えがまもなく出る。そして住宅用は19年からFITの10年が終了する。住宅向けPVは自家用エネルギーとしての利用拡大を目指し、産業用は中型を中心に蓄電池と一体化した安定電源として、新たな需要を目指す第2フェーズに入ってくる。
グローバルで最大の電源として普及しつつあるPVは、日本では14年の928万kWをピークに、16年は645万kWに減少してきた。これもFITが描いた〝宴〟の結果だが、コストが一層下がっていくことと合わせて18年以降は毎年400万kW前後をコンスタントに維持していく出荷量になっていくことが予想される。市場の今後の動向に対応し、国産PVメーカーには本腰を入れた世界戦略こそが、事業の発展に求められる。
電力調達の環境配慮、価格と対等条件にせよ
2017/11/15(Wed) 文:(水)
あまり耳慣れないが、「環境配慮契約法」という2010年に施行された環境省所管の法律がある。庁舎など国の機関や独立行政法人等が管理する建物・業務(サービス)・物品調達において、地球温暖化対策などへの環境配慮を強く促して契約(入札)する制度だ。いわば物品の購入という立場を最大限に活用、国自ら環境対策への範を示すことで、地方自治体にも同様の対応を促し、経済活動全般に環境保全との一体性を定着させるのが目的だ。
その制度に電力調達の分野があって、2018年度の基本方針がほぼ固まってきた。基本方針に記載する電気供給を受ける契約に関する基本的事項には、▽温室効果ガス等(CO2等)の排出程度が低い小売事業者との契約に努める、▽入札への参加資格者としてCO2排出係数の程度や再生可能エネルギーの導入状況など環境負荷の低減への取り組み状況――などを示す。これらの対応を点数化して70点以上獲得した事業者が入札に参加できること(裾切り方式と呼ばれる)になるが、制度発足後10年以上もたって多くの改善すべき点が指摘されている。抜本的な見直しは今までなされないままだ。
一つはこの環境配慮契約法による環境配慮を実施していない機関等が、対象となる契約件数・予定電力使用量の約1/3もまだあることだ。未実施の理由は「組織再編等への対応のため」「応札が見込めない」「長期継続契約によって安価な契約が可能」などが多かったという。いずれの理由も取り組みの工夫をすれば解決可能と思われるものばかりであり、法律によって半義務化されている制度に対して、こうした安易な言い訳が通ること自体が不思議である。
関係者は役所の物品調達には「会計法」という別の法律があり、ここで「安価な調達」が規定されそれを過度に重視すれば未実施になるというが、これでは環境省の強調する環境と経済な完全な統合や国民・企業に対するCO2対策強化の実行にも説得力を欠き、同省の弱腰は強く批判されるべきであろう。
もう一つは、この制度が国際的な温暖化対策の緊要性を反映していない時代遅れの価格の安さ優先方式になっていることだ。今の方式はあくまで競争入札前の参加資格者決定のためのものであり、価格と環境配慮を対等に評価する「総合方式」に早く是正すべきである。
衆院選公約に見られる政治家の二流さ
2017/10/20(Fri) 文:(水)
10月10日公示、21日投開票の衆議院選挙が始まった。公示前(議員総数475人)に圧倒的多数だった自民党(計290人)と公明党(35人)が現有議席の2/3以上を獲得して安倍晋三連立政権を維持するか、はたまた小池百合子東京都知事が率いる希望の党が旧民進党議員(57人)を吸収してどこまで議席を伸ばせるか、直前に新党として立ち上げた立憲民主党(16人)が足元を固められるかが焦点だ。
選挙戦の各党公約は2019年実施とされている消費税10%引き上げの是非と財政再建など9テーマでその独自性を競い、原発・エネルギー政策のあり方も主要な争点となっている。しかし、こうした経済政策および原発・エネルギー政策と表裏一体の「気候変動問題」に日本がどう対応するかという政策展開に関して、公約が提示されていないのには驚かされた。
わずかに立憲民主党が「パリ協定に基づく地球温暖化対策の推進」を掲げたぐらいで、他党は主要9テーマにすら入れていない。地球の温暖化進行が世界各地で異常気象による大洪水や干ばつ、海面上昇、生物種の激減などを発生させ、多くの人的・物的被害と数千万人と言われる「環境難民」を顕在化させている現実は、21世紀中最大の政治的課題といわれて久しい。日本でも近年の集中豪雨被害やサンマなどの漁場異変の出現が記憶に新しい。
気候変動問題への対応策は、各国とも化石エネルギーをどれだけ使えるかを中長期的に約束するものであるため、利害得失が直接ぶつかり簡単に国際ルールも合意できない。昨年11月にようやく発効した「パリ協定」とて、その具体化にはまだまだ多くのクリアすべき困難な課題がある。なにしろ国際的な気候変動問題への対応は、毎年開かれる先進国首脳会議において過去20年近く必ずテーマに取りあげながら、未だに目に見える成果を上げていないほど大変なテーマであり、欧州では政治勢力を左右するほどにもなっている。
だが、わが国の総選挙では公約にすら盛り込まれず、政策展開の方向も示さないというのは国民に対して無責任であり、いかに政治家が不勉強でかつ短期的な利益誘導しか考えていないという二流政治の典型でもある。グリーンカラー制服を着用して、清潔な環境派イメージ作りのために「環境」を利用する時代ではなくなっていることに、政治家は心すべきであろう。
一般家庭の温室効果ガス排出削減-環境省が支援に本腰
2017/10/06(Fri) 文:(一)
環境省が経済成長にもつながる気候変動対策として、一般家庭の温室効果ガス排出削減支援に乗り出す。日本が地球温暖化対策の新たな国際枠組み「パリ協定」で掲げた温室効果ガス削減目標「2030年度に13年度比26%減」を達成するためには、産業部門や運輸部門に比べて取り組みの遅れが目立つ家庭・業務部門の対策徹底が不可避。地球環境問題意識を高める意味でも、一般家庭に対する助成措置は有効だろう。
18年度予算の概算要求で、環境省は新規施策として経済産業省および国土交通省との連携による「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等による住宅における低炭素化促進事業」62億円、経産省との連携による「太陽光発電の自立化に向けた家庭用蓄電・蓄熱導入事業」84億円の計146億円を計上した。
前者では7000戸を対象にエネルギー消費を実質ゼロにするZEHの新築・改修費用を補助する。エネルギー消費を実質ゼロにするZEHについては、すでに国として標準化する方針を決めている。その具現化を助成措置で後押しする格好だ。一方、後者は19年以降、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度(FIT)による売電期間が終了する一般家庭が出てくる状況を踏まえ、2万7000戸を対象に家庭用蓄電池や蓄熱設備の設置費用を補助し、エネルギーを無駄なく使えるようにする。
また、業務部門についても経産・国交両省および一部農林水産省との連携による「脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業」で、前年度当初予算比1.5倍の95億円を要求。これにより従来の規模が大きい冷凍冷蔵倉庫に加え、小売店の冷凍冷蔵ショーケースにまで助成対象を広げて、環境負荷低減を徹底する姿勢だ。
環境省がまとめた15年度におけるエネルギー起源の温室効果ガス排出量は二酸化炭素(CO2)換算で前年度比3.4%減の11億4900万トン。家庭部門が同5.1%減の1億7900万トン、業務その他部門も同3.1%減の2億6500万トンと貢献した。空調の省エネ化や発光ダイオード(LED)照明の普及が背景とみられるが、これにとどめず持続可能な循環共生型社会の形成を目指したい。
バイオマス発電の急増とFIT制度見直し
2017/09/19(Tue) 文:(水)
わが国の再生可能エネルギー導入は全体の95%以上を太陽光発電が占めるといういびつな構造だったが、今年3~4月にかけてバイオマス発電の新たな認定申請が急増、政府関係者を慌てさせている。経済産業省は3年前に策定した「エネルギー基本計画」の点検・見直し作業を有識者の委員会で実施中で、バイオマス発電をどう扱うかも焦点となりそうだ。
バイオマス発電の急増は、FIT制度の開始以降4年間で計約600万kWの認定・稼働規模に過ぎなかったものが、16年度末に計約1100万kWの申請量になったという変化がそれを示した。背景にはバイオマス発電の買取価格が変更され、従来の24円/kWhが引き下げられて2万kW以上の場合21円となり、これがこの10月から適用となるため、旧価格での買い取りを目指した駆け込み的な申請が集中したとみられている。加えて、大手電力や新電力の計画する石炭火力の新増設が1000万kW以上もあり、パリ協定発効後に国際的に高まっている大量のCO2排出増への対応として、燃料の一部に海外で調達する安価なバイオマス資源を混入してそれを相殺、地域住民の反発を少しでも抑える狙いがある。
インドネシアやマレーシア、カナダなど海外で調達するバイオマス資源は木質チップ、パーム油などだが、購入価格が割安ということもあって現地の生物多様性や持続可能性に配慮しない不適切な資源調達になることが懸念されている。特に石炭火力に混焼するケースは分散型電源として小規模な設備を建設するのとは異なり、大型火力として立地させるのが一般的でその使用量も膨大となってタンカーで原油を年に数十回も運ぶ形と同様の方式となり、運搬上でのCO2排出量も決して小さくない。こうした懸念から環境省はバイオマスを混焼する大型石炭火力の環境アセスメントで、▽国際的な森林認証を得た燃料調達に努める、▽調達過程のCO2排出低減に努力――などの留保条件を指摘している。
経産省もFIT制度見直しの一環としてバイオマス発電の価値を再検討、買取価格対象の電源から外すかまたは一定の条件を満たした計画のみ認める、などの新たな対応を模索中だ。その理由としてはコストの60%を燃料費が占め買取価格低減の余地が少ないこと、環境保全への寄与があるのか、などを挙げている。
「核のごみ」最終処分問題を考える
2017/09/05(Tue) 文:(水)
8月下旬、世耕弘成経済産業相が高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分場として建設中のフィンランドのエウラヨキ市を訪れ、現場の視察とともに市長や議会関係者らと意見交換、わが国でこの20年近く停滞したままの処分場選定に関する知見や方法論を温めた。
経済産業省は7月、日本列島全体を核のごみ最終処分場に適しているか、それとも火山や活断層の近傍、土地の隆起・侵食が大きくないかなど8項目のチェックリストに該当する「不適地」を4色で色分けした「科学的特性マップ」を公表し全国の自治体に送付した。わが国でも最終処分地の候補選びが再度キックオフされた。これから年内にかけて、経産省と最終処分の事業主体である「原子力発電環境整備機構」(NUMO=電力会社の共同事業体)が全国で説明会や意見交換会などの理解醸成活動を一斉に展開する。
ただ、科学的特性マップは単に「より適性が高いと考えられる地域(科学的な有望地)」を地図上に色分け(自治体別は示さず)しただけで、肝心の社会経済的な条件の集約による対象地域の絞り込みはこれからだ。今回有望地に色分けされたところには国立公園もあれば人口密集地の大都会もあるし、さらには最も肝心な100~1000年わたって不可欠な安全性確保の担保方策や経済社会的措置(分かち合いの代償)などは今後の検討課題という。
核のごみ問題に限らないが、一般ごみの処分場や火葬場などの嫌忌施設の立地は古今東西を問わずいつの時代も大きな騒ぎとなり、収拾までには長い時間がかかる。自分が住んでいるところだけは避けてもらいたいというのも普通の感覚だろう。とすれば、そうした認識を変えてもらうに十分な“代償措置”と「国民のために」という深い思いが何よりも重要となる。
原発による電気は今から41年前に日本原電の東海発電所が供給して以来、これまで現世代がその利便性を享受してきた。自分が頼んだわけではないという理屈もあるが、経産省のいう次世代にツケ回しをしてはならないというのもその通りだ。しかし、一方で核のごみがさらに増加する原発再稼働を進めているのも同じ経産省である。ここは一度立ち止まり、原発を再生エネに全面的に置き換えたらどうなるかを提示してみたらどうだろうか。
安倍改造内閣は経済政策の大転換を
2017/08/17(Thu) 文:(水)
国民の支持率が政権発足以来最低の中で第3次安倍改造内閣が3日スタートした。発足後の首相会見の冒頭、加計学園問題で見られた説明不足や相次いだ閣僚の資質批判などを反省、国民に陳謝するという異例の船出となった。頭を下げた効果と新内閣への期待によって支持率が一時的に上向いたが、従来の政権運営とどう変わったかが目に見えるようにならない限り、低空飛行を変えるのは無理であろう。
そうした意味での注目は、サプライズ人事となった異端児・河野太郎氏の外務大臣登用だ。前回の行政改革担当相では脱原発推進や核燃料サイクル政策の見直しなどの持論を封印、内閣の方針に従うとして順調に閣僚を全うした。しかしその当時に比べて政治情勢が一変している。安倍一強の権力構造が崩壊しつつあり、一方で環境カラーを前面に出した小池都知事勢力が保守層を取り込みつつある。いわば政治の激動期に入ったとみることができ、こうした時こそ新たな自民党カラーを国民にアピールすることが必要だ。そのためには河野氏の斬新な持論を閉じ込めるのではなく、自由闊達な議論を踏まえ安倍政権として活用すべきではないか。
もう一つは、「アベノミクス」に代表される従来型経済政策の見直しだ。その切り口は環境政策との完全な統合であり、そうした対応が国内に新たな産業と雇用へのイノベーションを引き起こす可能性がある。環境政策との統合とは、気候変動対策を国の主要な経済政策やエネルギー政策の決定に対等に取り入れることであり、そのことが新たな産業起こしや関連ビジネスを活発化させることにつながる。
国連の報告書では、地球の気温上昇を産業革命前に比べ1.5~2.0℃上昇以内に抑えるためには2050年までに人為的なCO2排出可能量が残り1兆トンといわれる。世界の産業はこうした制約を意識してすでに再生エネやエコビジネスに邁進している。先日、イギリスとフランスがガソリン車などの内燃機関を2040年までに取りやめ電気自動車にシフトさせる方針を決めたのも、経済と環境政策の完全統合ともいえる。日本でも1000ヵ所以上に誕生したといわれる再生エネ等発電所が地域経済に新たな息吹を起こしているという。これまで環境政策に冷淡と言われてきた安倍政権が世界の潮流に遅れてはなるまい。
東芝の家庭用燃料電池撤退の波紋
2017/07/20(Thu) 文:(徐)
東芝が家庭用燃料電池の製造と販売から7月末に撤退する。原子力事業の損失で企業存続が問われる極めて厳しい経営環境の中、事業の選択に家庭用燃料電池(FC)は外された。日本が世界で初めて開発した固体高分子形(PEFC)のコージェネシステム「エネファーム」は、日本企業の世界一のモノづくりを世界に知らしめるエネルギーシステムだが、東芝の撤退でPEFCメーカーはパナソニックだけになる。固体酸化物形燃料電池(SOFC)のエネファームも京セラのデバイスで大阪ガスなどが実用化する。このためこれからはPEとSOが競争しあってコストをさらに下げ、革新技術を大きく開花させていかなければならない。
東芝の定置型FCは日本のFC開発そのものでもある。リン酸形燃料電池の開発に乗りだしたのが1978年。東京電力向けに1万1000kWの実証プラントを完成、200kW機を商用化した。そして家庭用を照準にしたPEFCの開発を1992年から開始。国の大規模実証をリードし2009年度から商用化、計8万台を販売した。14年度は2万1000台とトップの実績で、売上高182億円で黒字化した。この2年は赤字だったがエネファームはコストダウンの余地が大きく、東芝にとって現在は商用化の第一ステージであったはずだ。東芝はFC生産の子会社は存続、水素製造、貯蔵、利用の中で数kW以上のFC開発と販売は続けつつも、家庭用FCは水素事業の柱にならないと判断した結果である。
これから本番の家庭用FCを原発事業の犠牲にして撤退するのだ。エネファームは参入が最も遅かったパナソニックが現在は累計10万台を販売、増産対応を強化し、海外展開も進める。それは東芝との競争があったからこそ技術を強化することができたのだ。家庭用PEFCメーカー1社体制は、競争の面から大きなマイナスである。
一方、発電効率が高いSOが実力をつけてきているだけに、異なる機種の高レベルな競争が家庭用FCのコストダウンと、数百万台の普及につながっていくことを期待したい。夢のFCを、そこにあるFCにしてきた東芝技術陣の情熱が、パナソニックやSOメーカーの技術のパワーを増幅していくことを願っている。
エコカー原点は軽量化-NCVプロジェクトに期待
2017/07/04(Tue) 文:(一)
環境負荷が小さいエコカーのイメージは電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)で、もはやハイブリッド車に至ってはコモディティー化してしまった。だが、自動車産業が近代化していく歴史の中で、一貫して追求されたのが車体の軽量化。原動機の種類を問わず、限られたエネルギーで走行距離を伸ばし、動力性能も高める。軽量化はエコカーの原点といえる。
そんなことを思い起こさせてくれたのが環境省の音頭で、大学や研究機関、各種部材メーカーなど22団体で昨秋発足したコンソーシアム「NCV(ナノ・セルロース・ビークル)プロジェクト」。軽量・超高強度の次世代バイオマス素材、セルロースナノファイバー(CNF)を自動車部材に適用し、東京五輪・パラリンピックが開かれる2020年に、10%程度の軽量化を実現するNCVのプロトタイプを世界に披露するのが目標だ。
CNFは木質繊維(パルプ)をナノメートルサイズ(ナノは10億分の1)まで細かく解きほぐしたもの。セルロースミクロフィブリルと呼ばれる最小単位の繊維素は直径が髪の毛の1万分の1、3ナノ~4ナノメートルしかない。それでいて鉄鋼に比べ5分の1の低比重(1立方センチメートル当たり1.5グラム)で同等の曲げ強度と、5~8倍の引っ張り強度を持つ。こうした特性が自動車部品などの分野で、新たな補強材として期待を集める。ただ、バイオマス素材のCNFは基本的に親水性で、樹脂やゴムとの複合材料化は決して容易ではない。NCVプロジェクトでベクトルを合わせ、切磋琢磨しながら技術改新を成し遂げるのが狙いだ。
プロジェクトの2年目のスタートにあたり5月中旬、参加機関・企業の研究者が一堂に会する成果報告会が開かれた。ポスターセッションを中心に、まだ荒削りながら一部ではサンプル展示も。研究分野の違いはあっても目指すところは同じ。会場は熱気にあふれ、互いにシンパシーを感じているのが分かった。
会場の外にはCNF複合部材を実際に装着していくスポーツ車「トヨタ86(ハチロク)」が置かれ、疑似的に軽量化効果を体験する試乗も行われた。自動車市場の成熟が叫ばれる中、運転を楽しめる“王道のエコカー”があってもいい。
「カーボンプライシング」の検討と毒饅頭
2017/06/20(Tue) 文:(水)
環境省は今月2日、「カーボンプライシングのあり方に関する検討会」の初会合を開き、本格的な炭素税や排出量取引制度の導入に向けた議論を開始した。トランプ米大統領による「パリ協定」からの離脱表明があったものの、国際世論は世界第2位の温暖化ガス排出大国の身勝手な振る舞いに批判的だ。
パリ協定は世界の190ヵ国以上が合意して昨年11月に発効、2020年までに「加盟国は今世紀半ばの温暖化ガス低排出型発展の長期戦略を策定し通報すること」としている。いわば2050年までに温暖化ガス排出の80%削減という「低炭素社会」づくりのメニューを各国が提出することになるわけで、炭素税導入などを意味する環境省の「カーボンプライシング」検討もその一環だ。
炭素税制の導入は、あらゆる経済行為に地球温暖化の原因となる炭酸ガス(CO2)の排出に課税してその価格付けを一般化させるものだが、実はその変形が2012年から「地球温暖化対策税」として実施されている。現在、石油・天然ガス(LNG)・石炭に炭素排出トンあたり289円が課税されており、その税収分(16年度は約2600億円)がエネルギー対策特別会計として、省エネ・新エネ事業や低炭素型まちづくりなどの施策に補助されている。
ただ、この仕組みはあくまで温暖化対策に向ける財源を確保するためのものであり、あらゆる経済行為に炭素価格づけされ商品等の取引がなされているわけではない。当時の検討では、本格的な炭素税導入か財源確保のための税制か、という環境省と経済産業省の間で喧々諤々の議論となった。結局は環境省が産業界から強い反対が出されていた炭素税の導入を断念、自らの財源欲しさに経産省から出された“毒饅頭”を食べたと非難された。この時に我慢して毒饅頭に手を出さなければ、今回のような一から始める本格的な炭素税導入のきびしい論議や検討に要する時間も効率化できたかもしれない。
もちろん温対税を導入した当時に比較して今はCO2削減に関する政策的な優先度が大きく高まり、国際社会でも低炭素社会づくりに向けたビジネスが潮流となっている。しかし二度あることは三度ある。今回の炭素税制実現が再度、財源確保のための税制になってしまわないか、本当に使命感を持った制度が実現されるか先行きが心配だ。
「環境」と完全統合したエネルギー基本計画を
2017/06/07(Wed) 文:(水)
政府のエネルギー政策展開の大黒柱である「エネルギー基本計画」が2014年6月の策定後3年経ち、改定時期を迎えている。経済産業省はこの夏頃から実質的な作業に入る構えだ。今のエネルギー政策には重要課題が山積しており、米国が先日のG7サミットで「パリ協定」からの実質離脱方針を示した地球温暖化問題への対応とともに、骨太の計画にする必要がある。
14年に策定された基本計画は東日本大震災と東電福島第一原発事故を踏まえたエネルギー政策の大幅見直しを打ち出したことに特徴があった。すなわち電源の確保については、「再生可能エネルギーの最大限の導入」と「原発依存度の可能な限りの低減」と軌道修正、3.11以前の原子力主導+石炭・LNG火力による電力供給を大幅に変更した。同時に、需要家の選択肢を広げ市場競争による価格下げを実現するとして「エネルギーの総合企業化」の必要性を指摘、従来の垣根を取り払う電力・ガス事業の構造改革を推進するとしていた。
しかし、現実のエネルギー産業は海図なき航海に直面しているといってよい。確かに電力・ガス事業への新規参入は進んだが、小売料金はまだまだ下がっていない。原発の再稼働は徐々に出てきたものの、最終的にわが国の原発規模をどうするのかという一番肝心な点は依然あいまいにしたままだ。再生エネの導入は確かに飛躍的に拡大しているが、一方で認定取消し分が約2800万kWも発生、この後始末とともに系統接続問題も抜本的な解決の方向になっていない。さらには相次ぐ石炭火力の新増設計画による電気事業のCO2削減目標の達成見通しが困難という状況もある。
こうした混迷状況の原因は緊要な政策課題への判断をこれまで後送りしてきたツケがたまってきたためと思われる。その一つが原発依存度の現実的な設定であり、それを前提にした各種電源の組み合わせの見直しであろう。再生エネの導入拡大もそれによって変化するし、化石燃料への依存度も明確になり、しいてはCO2削減への対応もはっきりさせることができる。今やエネルギー政策は温暖化対策と一体であることを強く認識し、「エネルギー・環境基本計画」として見直すべきではないか。もう一つは「総合エネルギー企業化」のグランドデザインを政策当局が提示することだろう。
CO2排出量、2年連続の減少-予断は許さない
2017/05/15(Mon) 文:(一)
日本の温室効果ガス排出量が2年連続で減少した。環境省が確定した2015年度の排出量は二酸化炭素(CO2)換算で前年度比2.9%減の13億2500万トン。正式に国連気候変動枠組み条約(UNFCCC)事務局に提出された。昨年末にまとめられた速報値は同3.0%減の13億2100万トン。算定方法の見直しなどを反映した結果、減少率が0.1ポイント下がり、排出量で400万トン増となった。
14年度に続く2年連続の減少は、09年度以来6年ぶり。08~09年度はリーマン・ショックによる経済活動の停滞が主因だった。14~15年度は緩やかに経済が回復する中で省エネルギー機器・設備が普及し、再生可能エネルギーの導入も進んだことで、大部分を占めるエネルギー起源のCO2排出量が減少した。また、15年度は原子力発電設備が再稼働したことで、約410万トンの省CO2効果があった。
政府は排出量削減の暫定目標として20年度に05年度比3.8%減を掲げていたが、同5.3%減で前倒し達成。また、13年度比では6.0%減になり、地球温暖化対策の新たな国際枠組み「パリ協定」で日本の国際公約となった30年度までに13年度比26%減の達成に向け、滑り出しとしては順調に見える。
エネルギー起源のCO2排出量は前年度比3.4%減の11億4900万トン。産業部門や運輸部門に比べ、これまで取り組みの遅れが目立った商業施設やオフィスなどの業務その他部門と、家庭部門も大幅に減少した。空調の省エネ化と発光ダイオード(LED)照明の普及が背景だ。
ただ、予断は許さない。化石燃料からのダイベストメント(投融資撤退)が世界的な潮流となっても、日本国内では依然として石炭火力発電所の建設計画が多数ある。さらに、温室効果ガスだがオゾン層を破壊しない代替フロン(冷媒)として普及したハイドロフルオロカーボン類(HFCs)の排出量が、CO2換算で同9.6%増の3920万トンと増加基調にあり、省エネの重い足かせになってきた。
今世紀後半に温室効果ガスの排出実質ゼロを目指す「パリ協定」のハードルは決して低くない。今後も相当な努力が必要だ。
トランプ政権、パリ協定「無視」の歴史的責任
2017/04/26(Wed) 文:(水)
トランプ政権による気候変動問題への対処方針がほぼ明らかになってきた。3月29日に示した大統領令の中の「エネルギー安全保障と経済成長の推進概要」によれば、気候変動問題に関連して次の事項が提示されている。▽各行政機関長は国内エネルギー資源の開発・使用の負荷になり得る全ての行政措置を見直し、そのためのプロセスを見直す ▽EPA長官は「クリーンパワープラン」見直しのために必要な措置を直ちに実施。これら考え方の通底は、2030年に向けた温室効果ガス・CO2の国別削減目標の設定と達成をルール化した「パリ協定」の否定であり、事前に指摘されていた「パリ協定の無視」の政策化、実質的なパリ協定の脱退化でもある。
これに対して、わが国は安倍晋三政権の是認姿勢や責任意識の希薄さによるマスコミ界の批判的意見の欠如が目立つ一方で、一部の環境NGOらが共同または単独で米国方針を指弾している。ちょうど、パリ協定で定める今世紀後半に向けた長期温暖化対策の取り組む方向を議論中なのに動きが少なすぎる。
気候変動問題が国境を超える人類不可避の地球環境問題として提起されてからほぼ半世紀たつ。この間、科学者は曲がり道しながらも数次の研究成果をあげ、科学的な因果関係の結論として温暖化の進行と脅威を注意・喚起→警鐘→警告→確証へと最高水準にまで高めた。延べ2000人以上が「対応策の実施と技術の適用に時間がない」との見解も強調してきた(5次にわたるIPCC報告書など)。後は、最も意識と行動が遅れている政治の世界だが、G7サミットはじめ十分な主導力が見えず、すでに30年以上も停滞して責任を果たしていない。しかし、今日の政治家の責任は30年前とは明らかにその度合いが大きく異なっている。一つは科学的材料の十分性、二つは今回明らかになったCO2許容総体排出量=残り1兆t、三つはこれまで起きた気候変動被害の大きさである。
こうしたことの理解の上で、国際社会がようやく実現したパリ協定を米国が「無視」の行動をとりこれに同調する国が増えれば、トランプ大統領には「温暖化を加速させた最悪の米大統領」として、水没した国や気候難民から裁判を提起されるかもしれない。気候変動問題では一日も早くトランプ氏だけではなく政治家が覚醒してもらいたいものだ。
【これより古い今月のキーワード】 【今月のキーワード 最新版】