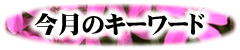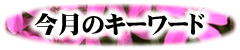[過去94~109 回までの今月のキーワード]
若者による「ダイベストメント宣言」の行方
2019/06/28(Fri) 文:(水)
今月は月末には大阪市でG20の首脳会議があり、わが国の政治経済問題へのパフォーマンスが世界中の注目を集めることになる。安倍晋三首相にとっては、来年の五輪・パラリンピックを控えて会議を成功裡に終わらせ、「日本ここにあり」という存在感に弾みをつけたい思いであろう。
G20の首脳会議に向けた農林水産・貿易・財務・エネルギー・環境分野などを担当する大臣会合はすでにいくつか開催されており、共同宣言などの成果が出されている。福岡市で今月8~9日に開催された「G20財務・中央銀行総裁会議」もその一つだ。ほとんど報道されていないが、その会議に「パリ協定」関連の要望書が提出された。提出者は環境NGOの50.orgJapan で、「ダイベストメント宣言」というタイトルがつけられており、宣言内容を実現するよう財務大臣、日本銀行総裁、金融庁長官およびみずほ、三菱UFJ、三井住友の各フィナンシャルグループのトップに求めている。
宣言では「預金先の銀行および投資先の金融機関が、地球温暖化を促進するビジネスを支援し続ける場合、私・弊団体は2020年東京オリンピックまでに『地球にやさしい預け先』を選びます」という内容。要は、わが国のメガバンクが世界の1位(みずほ)、2位(MUFG)、4位(SMBC) を占める石炭火力事業への投融資を引き上げるように促し、それがダメな場合は貯預金口座を他の金融機関に移すという“宣戦布告”である。
NGOの350Japan は、「市民の力で100%自然エネルギー社会を」をキャッチフレーズに、若い世代を中心にした国際的な組織で、▽化石燃料を掘り出さない、▽お金の流れを変える、
▽脱炭素社会の構築――を活動の目的としている。「350」という名称の由来は、今まで通りの地球生態系の維持のためCO2濃度を350ppmまで低減させる必要があると語ったNASA宇宙研究所の前所長ジェームズ・ハンセン博士の発言を引用している。こうしたポリシーに共感する若い世代が日本にも増えてきており、企業だけではなく大学・組合等でも活動が活発化しているという。しかも今回は日本の市民運動では珍しい直接行動を予告したメガバンクへの警鐘となった。ダイベストメントの行方もさることながら、若い世代による行動型運動の行方にも注目したい。
「カーボンリサイクル技術」への賭け
2019/06/12(Wed) 文:(水)
6月の日本はG20(20ヵ国・地域会議)の季節でもある。月末に大阪で開かれる首脳会議に向けて、エネルギー・環境大臣会合など特定分野の一連の会合も開催され、地球温暖化対策や廃プラスチック問題への国際的な共通の取組が決定される。
温暖化対策の行方に関して、最近にわかに内外で注目されているのが「カーボンリサイクル技術」の実証研究と実用化だ。これまでもCO2を吸収・貯留する技術として「CCS」は実証化されつつあるが、さらに最近はこのCO2を炭素資源(カーボン)として捉え、回収した後に多様な炭素化合物に再利用(リサイクル)する「CCUS」への取組強化が各国で重点的に進められている。
わが国も、昨年後半から同技術を温暖化対策の“切り札”と位置づけ、CO2を対象物質に▽回収コストの低減、化学品・燃料・鉱物などの素材資源に転換する技術の開発、▽炭素由来の化学品・資源等の用途開発――を官民挙げて展開中だ。今年2月にはその推進母体となる「カーボンリサイクル協議会」がスタート、主要業界団体などが構成メンバーとなって炭素イノベーションに挑戦する。加えて、経済産業省は近く「カーボンリサイクル技術のロードマップ」をまとめ、国際協調のもとでそれに邁進する。
カーボンリサイクル技術実用化への挑戦は、見方を変えればCO2削減対策が手詰まりに陥っている裏返しでもある。昨年12月の気候変動国際会議(COP24)では、地球の平均気温上昇を1.5度~2度未満に抑える考え方が示されたが、これを実現するためにはわが国はじめ主要国がすでに提出しているCO2等削減計画の大幅強化が必至となる。特に、再生エネ導入と原子力発電の稼働に出遅れているわが国は、2030年の削減目標さらにその先の50年における80%削減に向けた有力な方策を見定めることができず、カーボンリサイクルという新たな技術開発に“神頼み”のようにすがることになった。
しかし、一つの未知の技術に頼ることの危険性は今さら指摘するまでもなく、加えてそれが失敗した場合の対応策も未定であり、温暖化の進行は進むばかりだ。ここはもう一度原点に立ち返り、化石燃料の利用をどうしたら効率的にできるか、再生エネをどこまで拡大できるか、地道な対策も再検討すべきではないか。
皐月の風をいっぱいに受けて
2019/05/22(Wed) 文:(山)
「甍の波と雲の波 重なる波の中空を橘かおる朝風に 高く泳ぐや鯉のぼり」―5 月といえば鯉のぼりというイメージがあった。田舎にいた子供のころ、風に泳ぐ鯉のぼりを見ながら、大声で歌った記憶がよみがえる。だが、今の東京では鯉のぼりはほとんど見られなくなった。
その一方、皐月の風を受けて回転している発電用風車をあちこちで見かけるようになった。NEDOによると、国内の風力発電の累計導入量は昨年3 月末で2253 基、総設備容量は350 万2787 kW。10 年前の167万4280kWからずいぶん増えたが、それでも英国など欧州と比べると雲泥の差だ。台風の多い日本では強風に耐える風車にするために設置コストがかさむことや風況のよい平地が少ないこともあり、風力よりも太陽光を重視する傾向にあった。だが、昨年11 月下旬にいわゆる洋上風力開発促進新法が成立し、今年4 月に施行された。
共同通信は4 月26 日付で『洋上風力発電普及法に基づく国の調査に対し、北海道、青森、岩手、秋田、山形、千葉、新潟、佐賀、長崎の9道県が「適地がある」と報告したことが分かった。年内にも第1 弾の「促進区域」を指定する見通しだ』と報じた。洋上風力発電は海中に基礎をつくらなければならないことや塩害対策、建設や故障時のメンテナンスのための船舶、電気を陸に送るケーブルなどコストがかさむ。また漁業者の理解を得ることも必要になる。設備の寿命がきた時の原状回復も大変な作業になると思われる。
それでも陸上風力に比べて発電量が稼げる洋上が注目されているのだろう。ひとたび事故が起こったら大惨事となる原子力発電や温室効果ガスを排出する石炭火力の恐怖から逃れることができるなら、多少コストがかかっても洋上風力の普及を図ってほしい。周囲を海に囲まれている日本にとって最適な電源になるのではないだろうか。
IMOによる船舶NOx規制への対応が急務
2019/04/25(Thu) 文:(一)
停泊中も黒煙を燻らせている煙突は船のシンボル。大型船だと船会社のロゴマークを配して、カラフルにデザインされていることも多い。そんな船舶からの排ガスに、厳格な環境規制の網がかけられる。港を描いた絵画にもしばしば登場するシーンだが、風情に浸るだけでは済まない現実がある。国際海事機関(IMO)は2020年1月、船舶排ガスの環境規制を本格導入する。排ガスの硫黄酸化物(SOx)を減らすため、燃料のC重油に含まれる硫黄分濃度を現状の3.5%以下から0.5%以下に制限する。公海を行き来する船舶運用は一国の政府による規制では縛りきれず、16年10月に開かれたIMOの海洋環境保護委員会で導入が決定された。
C重油は原油を精製して液化石油ガス(LPG)、ガソリン、ナフサ(粗製ガソリン)、灯油、ジェット燃料、軽油などを抽出した残渣。成分としては道路舗装などに使われるアスファルトに近い。日本の石油業界は原油の大部分を重質の中東産に依存していることもあり、現状では石油精製で一定量のC重油やアスファルトができてしまう。低硫黄のC重油を量
産するには、中東以外から硫黄分の少ない割高な軽質原油を調達して原料にするか、重質油熱分解装置の増強が必要になる。ただ、石油業界にとって燃料油は主力の自動車向けガソリンを含め、需要が頭打ちの成熟商品。2年半前に規制導入が決まってからも、動きは鈍かった。
船会社側で既存船にSOxの除去装置「スクラバー」を取り付ける方法もあるが、IMOはSOx規制に続き、25 年には温室効果ガスの二酸化炭素(CO2)を削減する燃費規制導入も決めている。IMO加盟国は50年までに、海運分野のCO2排出量を08年比で半減することで合意しており、段階的な規制強化により既存船での対応が難しくなる状況も想定されている。欧州ではC重油に代わるLNG(液化天然ガス)燃料船導入の動きも目立つが、まだ日本は実証事業レベル。IMO規制はSOxや粒子状物質(PM)による人の健康や環境への悪影響を低減するため世界一律で実施されるものであり、我が国も環境先進国として、適切に対応していくことが必要だ。
原子力発電所の畳み方を説明してほしい
2019/04/18(Thu) 文:(水)
今夏の参議院選挙を前に、わが国の原子力発電所のあり方をどうするかの議論が盛んになってきた。小泉純一郎元首相を一枚看板とする原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟(原自連)は、開会中の通常国会に野党を通して「原発ゼロ法案」を提出しているが、与党からの握り潰された状態が続く。先日、原自連側は経団連の中西宏明会長に公開討論会を申し入れたが、実現していない。実現しない背景には、統一地方選と参院選を前に原発是非論議をヒートアップさせたくない首相官邸筋の“要請”があったと言われている。
小泉元首相が展開する「原発廃止論」を要約すると、▽多重防護をとっているから絶対安全、▽電源コストが一番安い、▽CO2を出さないクリーンエネルギー――という論拠が今日崩壊し、これまで政治・行政・電力会社がウソをついていたというもの。こうした主張は勇ましくかっこよく国民受けもする。しかし原発廃止論には致命的な欠陥がある。仮に原発を畳むとした場合の国民への傷みを具体的に提示していないことだ。
仮に原発をこの先10年で畳んだらどうなるか。まず、すでに廃炉を決定した24基(検討中含む)に加えて、新たに36基の座礁資産が生まれ1基350~500億円といわれる廃炉費用に加えて運転停止による膨大な固定費の未回収分が発生する。さらに巨額な資金を投じて推進してきた再処理などの核燃料サイクル事業が中止となり、後始末におそらく20~30兆円近くの国民負担が生じよう。そうなると国策故になんとかバックエンド事業に協力してきた青森県はちゃぶ台をひっくり返し、一時貯蔵の使用済み核燃料や放射性廃棄物の引き取りを迫る可能性がある。また原発立地県における雇用問題の発生など地域経済への打撃もある。一方で福島第一の事故処理には総額20~40兆円もかかるという試算も明らかになった。
つまり原発を畳むとすればそのため資金だけでもゆうに最低50兆円、場合によっては100兆円ともなり、その大半が今後の国民負担となる。さらにパリ協定で約束したCO2削減は、2030年目標どころか50年の△80%は再生可能エネルギーだけでは到底達成できず、単一エネルギーに依存するリスクが増大する。小泉元首相はそうした原発の畳み方に是非具体的に触れて欲しいものである。
“共生圏”での電力地産地消に期待
2019/03/22(Fri) 文:(一)
横浜市が2月上旬、脱炭素社会の実現に向けて東北地方の12市町村と再生可能エネルギーに関する連携協定を結んだ。連携先の自治体で発電された太陽光、風力、バイオマスをはじめとする再生エネを横浜市内の需要家へ供給するスキームを検討し、連携自治体全体の地域活力創出につなげる「地域循環共生圏」を構築していく。昨秋以降、九州で再生エネの発電電力を使い切れない状況が生じて出力制御が実施されるなか、共生圏という枠組みで電力地産地消を目指す取り組みに注目したい。
横浜市が協定を結んだのは青森県横浜町、岩手県北にある久慈市、二戸市、葛巻町、軽米町、洋野町、一戸町、普代村、野田村、九戸村、福島県の会津若松市と郡山市。再生エネに関する自治体連携では全国最大規模になるという。
地球温暖化対策の新たな国際ルール「パリ協定」発効に呼応して横浜市は2050年を見据え、徹底した省エネとともに市内で消費する電力を再生エネへ転換し、21世紀後半早期の二酸化炭素(CO2)排出量実質ゼロをゴール(目指す姿)とする「ゼロカーボンヨコハマ」を掲げる。林文子市長は「横浜市だけで大量の再生エネを確保するのは難しく、市町村の協力が必要。新しい可能性を持った連携で日本のモデルにしたい」と話す。
同市は昨夏、脱炭素社会の実現に向け、低炭素化をビジネスの視点から目指す企業ネットワーク「日本気候リーダーズ・パートナーシップ(Japan-CLP)」(事務局=地球環境戦略研究機関)と地方自治体として初めて連携協定を締結。その際、市が開発を進める「環境モデルゾーン」の企画や実証に参画してもらうとともに、再生エネを市域外から調達する仕組みづくりも共同で検討するとしていた。新たな形の官民連携の成果ともいえるだろう。
横浜市では16年からトヨタ自動車、東芝、岩谷産業の3社と神奈川県および川崎市と共同で、横浜港にある市の風力発電施設「ハマウィング」の発電電力で水素を製造し、京浜臨海部の事業所で燃料電池フォークリフトを稼働させる低炭素水素活用実証プロジェクトも始まっている。再生エネを調達できることが、企業立地や競争力に影響を及ぼす時代を迎えている。
クリーンイメージ・再生エネの再出発
2019/03/07(Thu) 文:(水)
環境にやさしく地球温暖化対策にも不可欠とされる太陽光・風力発電など再生可能エネルギー事業の展開に異変が起こっている。今年1月中旬、全国からメガソーラー開発事業に反対する計17余団体以上のグループが集まり、地域の開発計画に対する多くの問題を指摘、環境省や経済産業省に対して環境アセスメント制度の見直しや、FIT制度による認定取り消し措置などを強く要請した。この「全国メガソーラー問題中央集会」は昨年も開催されており、太陽光発電等の立地開発が土砂災害や景観の改変・破壊、濁水などの環境問題を引き起こし、生活する地域住民に多大なマイナス影響を及ぼしているという。また、事業化における住民への説明も不十分で、条例等の対象になっていないことを理由に、理解を得るための説明会ではない形式的な開催も目に付くという。
こうした住民側の問題提起は、国の環境アセスメント制度への不満が背景にある。現行制度では太陽光発電事業はアセスの対象になっておらず、遅ればせながら環境省が対象にする検討に入った。すでに太陽光発電のFIT認定規模はおよそ60GWという規模に達しており、遅きに失したといえる。また風力アセスの緩和なども検討されているが、バードストライクなどが各地で見られている。
昨年11月、経産省は2012~14年にFIT法の設備認定を受けながら未だに未着工の太陽光発電計約20GWに対して、工事着工の新たな期限や買取価格の引き下げ措置などを実施する方針を決めた。これへの事業者対応で目立ったのは、単なる投資物件としての認定証の転売による利ザヤ稼ぎや、崖地など不適切な立地場所による遅延ケースなどだったという。なかには反社会的勢力が事業に関与して事業がストップ、およそエネルギー供給者としての責任のかけらも見られなかったという例も相当あったようだ。
これまで再生エネの推進は原子力発電の頓挫が長引く中、化石燃料に代わる新たな時代の“寵児”としてもてはやされ、その負の部分にスポットがあまり当たることなくクリーンなイメージと手厚い財政的保護や制度的な優遇を受けてきた。しかし、この先2年以内にはFIT法の抜本見直しによる固定価格買取制度の縮小・廃止措置が想定されており、本当の意味での「自立化」ということが求められている。
太陽光発電と同じように、水も使う場所で〝創省蓄〟
2019/02/22(Fri) 文:(山)
「ネットゼロウォーター」という言葉を御存じだろうか。弊誌「創省蓄エネルギー時報」は題字の示す通り、主に電気を中心としたエネルギーの創造、節約、貯蔵に関する報道が主体である。一方、電気と同じように人々の生活に欠かせない水の世界でも〝創省蓄〟を目指した取り組みが始まった。
わが国の水道事業の民営化を進める改正水道法が昨年12月に成立した。野党は海外では民営化による料金高騰や水質悪化の問題が起こり、公営化に逆戻りした例が少なくないと反対したが、与党が押し切った。わが国の水道民営化がうまく機能するかどうか心配なところである。
こうした中で、水を上手に使いまわす技術を普及させようという動きが出てきた。欧米では緑地を使って水資源を循環利用する「ネットゼロウォーター」が普及しているという。この仕組みを日本でも取り入れようと、有志が昨年6月にネットゼロウォーター研究会を立ち上げ、今月15日に東京で第1回セミナーを開いた。
ネットゼロウォーターは雨水や建物で使った水を下水に流さずに緑地に集め、緑地と土壌を使って濾過し、再利用する仕組みだ。水の濾過に適した土壌を通過した水は上水と下水の中間の中水にまで浄化され、地下のタンクに流れ込んで貯められる。タンクは太陽光発電でいえば、電池の役割といえるだろう。
ネットゼロウォーターの仕組みを海外で視察した同研究会の坂本哲日比谷アメニス(東京都港区)水事業準備室長は「米国では浄化した中水を潅水や工場の冷却水、トイレなどで再利用していた」という。住宅の屋根に設置した太陽光発電は使う場所で電気をつくる。これと同じように水もその場所で生み出していくという考え方だ。中水をうまく活用できれば、コスト低減にもつながるだろう。
国連の持続可能な開発目標(SDGs)では「安全な水とトイレを世界中に」をはじめ、水に関連した項目が少なくない。水は人間の生命維持はもとより、あらゆる産業にとって欠かせないものである。電気と同じように大事に使おうという挑戦に期待したい。
「卒FIT」はプロシューマーへの道
2019/02/18(Mon) 文:(一)
米国の未来学者、アルビン・トフラーは1980年の著書「第三の波」で、消費者が生産活動にかかわるプロシューマー(生産消費者)の出現を予言した。エネルギー分野では、住宅用太陽光発電(PV)の余剰電力を買い取る2009年に始まった固定価格買い取り制度(FIT)利用者がそうだろう。住宅用PVの買い取り期間は10年で、今年11月に期間満了が出始める状況となり、卒FITを迎える利用者を巡る動きが活発化してきた。
FIT導入当初は、環境意識の高い消費者が敏感に反応してPVを設置。だが、太陽光パネルの低価格化とともに、PVシステム販売をビジネスチャンスとみて参入した事業者が売り込み合戦を繰り広げたこともあり、「元が取れるなら」という費用対効果で購入を決める一般的な耐久消費財に仲間入り。FITに契約期限があることさえ失念している利用者も相当数に上り昨秋以降、政府が周知徹底に乗り出し、新聞に全面広告を掲載したことは記憶に新しい。
FIT電源の買い手となっている電力大手(旧一般電気事業者)各社は、経済産業省の指示により昨年末までに買い取り継続の方針を表明。具体的な買い取りメニューの検討作業に入っている。住宅用FITの対象となっているPVは出力10kW未満と小規模だが、買い取り期間終了後は消費者全体で担っている賦課金と切り離れ、二酸化炭素を出さない“CO2フリー”という環境価値を持った電源になる。将来のVPP(仮想発電所)の電源とも目され、電力自由化で参入した新電力も卒FIT電源の買い取りに意欲を見せており、あの手この手のアプローチが繰り広げられそうだ。
ただ、再生可能エネルギー導入促進を目的とした賦課金がなくなることで、経済合理性のある買い取り単価はFIT導入当初(48円/kWh)の5分の1近くになると予想されており、必然的に「売らずに使う」という選択肢も浮上してくる。蓄電池は家庭用でもまだ高価で手軽に設置できるものではないが、普及してきた電気自動車(EV)を活用するシステムも製品化されており、消費者の選択肢は着実に広がっている。プロシューマーとして、いよいよ“賢い選択”が求められる。
2019年キーワードは、持続可能な社会づくり
2019/01/25(Fri) 文:(水)
平成最後の2019年。年頭に様々な新年メッセージに接した。昨年12月に難産の末に合意された「パリ協定の実施ルール」の余韻もあったためか、ほぼ共通していたのは気候変動対策への対応強化とそれと並走する「持続可能な開発目標」(SDGs)というコンセプトだった。
原田義昭環境相は、「これからの環境政策は世の中を脱炭素型かつ持続可能な形へと転換させ、イノベーションを引き起こし新たなマーケットを創出していく。環境政策が成長の牽引役となっていくことが重要」。世耕弘成経済産業相は、「パリ協定は今世紀後半に温室効果ガスの排出を正味ゼロを目指すとしており、エネルギー政策には脱炭素化が強く求められる」。
JFEエンジニアリングの大下元社長は、「193ヵ国で合意されたSDGsへの関心が世界中で高まっている。環境・エネルギー・インフラ分野での世界貢献が求められており、当社の暮らしの礎を創り・担う使命とまさしく同じ方向性」。変わったところでは、出生証明付き(電源地の証明)再生エネを全国の新電力や市民発電所などに売電しているみんな電力の大石英司社長のメッセージ。「テクノロジーを使って、電気の生産者と消費者を顔の見える関係でつなぎ、皆さんの電気代というお金が故郷や復興地の電気生産者にしっかり渡って、有効活用されるようサービス改良に励んできた。2019年はこの顔の見える電力を一層広めて当たり前にするのが第一の目標です」。
圧巻は、年頭に際しての記者会見で述べた中西宏明経団連会長(日立製作所会長)の発言がサプライズだった。
「お客さんが利益を上げていない商売で利益を上げるのは難しい。一方で、稼働しない原発に巨額の対策費がつぎ込まれているが、8年も製品をつくっていない工場(原発)存続のために電力会社が費用をつぎ込むなど、経営者として考えられないことをやっている」という内容だ。経団連会長として日本の電力業界に対する強い危機感、さらに出身会社の日立製作所のビジネス展開に目を曇らせている。共通するのは、政府が本気で原子力再編・統合の牽引力を果たしていないことであろう。東芝がWHの原子力に潰され、重視された原発輸出が実らず、今の国内原発のありようでは日本のインフラ産業は持たないとの危機感かもしれない。
産業界も気候変動対策に舵を切る
2018/12/26(Wed) 文:(山)
清少納言の「枕草子」には「ただ過ぎに過ぐるもの」のとして「ほ(帆)かけたるふね(舟)。人のよはひ(年齢)。春、夏、秋、冬」とあります。地球の回転の速度は変わっていないのに、歳を重ねるごとに時の流れが速くなっていくように感じます。人間の感性は1000年以上も前とそうは変わらないのかもしれません。というわけで“早いもので”今年も残すところ半月足らずとなりました。そこで本誌は「創省蓄エネルギー」今年の十大ニュースを掲載しました。
話はかわりますが、今年はわが国の産業界で「脱炭素」に向けた流れが大きく加速しました。事業で使うエネルギーのすべてを再生可能エネルギーでまかなう「RE100」に加盟した日本企業は昨年まで3社でしたが、今年は10社が加わりました。これは十大ニュースでも取り上げています。
また日本気候リーダーズ・パートナーシップ(J-CLP)は国連気候変動枠組条約第24回締約国会議(COP24、ポーランド・カトヴィツェ)が始まる前の先月30日、「パリ協定に基づく長期成長戦略への提言」を発表しました。J-CLPは「脱炭素社会へ先陣を切ることが自社にとって次なる発展の機会」と捉え、2009年に設立され、現在、大企業を中心に93社が加盟しています。
提言は脱炭素社会の方向性を共有、目的地とそこに至る経路について具体的なシグナルを発することが必要として、以下の5項目をあげています。①国民全体で気候変動への危機感を共有 ②「脱炭素ビジネス立国」を掲げる ③2050年温室効果ガス排出ゼロ ④カーボンプライシングと公共投資による脱炭素インフラの整備 ⑤脱炭素ビジネスへの「転換マネジメント」の仕組みを構築。
このように気候変動対策に後ろ向きとみられていた産業界も大きく舵を切りつつあります。世界的にも脱炭素に着手した企業がビジネスで優位に立てる時代となってきたように感じます。来年こそ産業界だけでなく、国民全体が脱炭素社会の形成に向けて行動を起こす年ではないでしょうか。本誌もその一助となるよう頑張りますので、引き続きご愛読のほどよろしく願い申し上げます。
いびつな日本の再生エネ事業を脱却する契機に
2018/12/06(Thu) 文:(水)
経済産業省が打ち出した事業用太陽光発電(PV)の未着工案件に対するFITの買取り減額措置が侃々諤々の議論になっている。自民党の再生可能エネルギー普及拡大議連(柴山昌彦会長)は先月8日に会合を開き、大手PV事業者から減額措置案に対する意見をヒアリングしたが、自民党会合では珍しく経産省への過激な批判が集中した。
例えば、これまで200件・250万kW以上の太陽光発電関連ファイナンスを扱ったという法律事務所の弁護士は、「今までで最悪の制度変更だ。経産省が減額措置案を発表したわずか1週間で25億、40億、16億円の融資がストップした。新規案件だけではなく、全く問題なくもう少しで運転開始する事業までリスクありとみられている」と、事業継続の危機感を強く訴えた。続けて法制度の運用面でも瑕疵があると指摘。FIT制度の買取価格と期間の20年は法律で保証されているものであり、これの着工が遅れているからといって過去に遡って不利益な変更をすることは法治国家ならば「禁じ手」だ。少なくとも告示変更などの安易な対応ではなく法律改正が必要なはずと指摘、FIT制度に対する内外の信頼を失墜させると断じた。業界関係者によると、今回の措置によって大手金融機関が投融資しているPV案件の計3000億円程度が焦げ付く可能性があるという。
経産省の未着工案件に対する減額措置案は、再生エネの普及拡大に真面目に取り組む良質の事業者と一時の利潤稼ぎだけを狙いとした悪質事業者を峻別し、中長期的な再生エネの主力電源化に脱皮するショック療法ともいわれる。ただ、ショック療法とは言っても日本の再生エネ市場が成熟し、制度変更リスクを十分吸収できる余地があればの話であろう。
特に今回議論になっているのが、着工遅れの原因が事業者自らの責に帰さない、例えば環境アセスや林地開発等の許認可遅れのケースの扱いだ。確かに手続きに4~5年もかかる事例があるかもしれない。しかし冷静に見れば、急斜面の崖地や景観を無視した乱開発など近隣住民との紛争事例がとみに最近増えているようであり、こうした強引な開発手法が時間のかかる要因にもなっているわけで、いびつになっている日本の再生エネ事業を脱却させる契機かもしれない。
再生可能エネルギーの自立と連系を
2018/11/22(Thu) 文:(一)
9月上旬の北海道胆振東部地震では、離島を除く道内の全電源が停止する大規模停電(ブラックアウト)に陥った。九州では10月半ばから11月にかけての週末(土日)、一部の太陽光発電所や風力発電所を止め、出力が抑えられた。ブラックアウトは地震の被害が北海道電力の想定を上回り、強制的に供給エリアを遮断する強制停電を繰り返しても、電力供給が追いつかなかったことが原因。一方、九州電力が実施した再生可能エネルギーの出力制御は、工場や事業所が休みになって電力需要が減る週末の日中、太陽光発電や風力発電がフル稼働すると、供給過剰になってしまう恐れがあったため。何とも対照的な事態だ。
電力の送配電は需要と供給を一致させる“同時同量”が原則。電力システム改革の時流と相まって再エネの導入が進んだが、さまざまな課題も浮き彫りになってきた。今後の再エネ活用は自立化と、連系がキーワードになるだろう。
自然豊かな北海道は風力発電の先進地で、広大な土地を生かした大規模太陽光発電所(メガソーラー)も多い。一方の日射量に恵まれた九州はメガソーラーのメッカとなった。両発電方式とも自然の気象条件によって出力が大きく変動する。送配電を担う電力会社にとって、出力変動が大きい再エネは扱いにくい存在。こうした再エネ電力が増えてくると必然的に、電力会社側の調整は難しくなってくる。実際、北海道電によるブラックアウトからの復旧過程でも、風力発電などの接続は影響が出にくいように、火力発電所などが再稼働して電力系統がある程度の規模になってからになった。ただ、北海道のブラックアウトでも太陽光発電システムがある家庭の85%が自立運転モードに切り替えて発電電力を自家利用し、蓄電池を併設した家庭では2日間程度、普段通りに生活できたという。
分散型電源の再エネに蓄電池を組み合わせれば非常時、マイクログリッド(小規模電力網)として運用できる可能性が広がり、送配電網との連系も容易になる。再エネ導入に併せて、蓄電池や電力を地域間で融通し合う連系線などを整備する仕組みが求められる。
アクセルとブレーキを同時に踏む再生エネ政策
2018/11/07(Wed) 文:(水)
経済産業省が最近打ち出した再生可能エネルギー政策が波紋を呼んでいる。一つは8月に示した再生エネの買取価格制度(FIT)の運用で、現行の買取価格(住宅用太陽光発電=26円/kWh、風力発電=21円など)を4~5年先にはそれぞれ半分以下にするような対応措置を示した。もう一つは、先月関係する審議会が事務当局案をほぼ了承したもので、2012年以降3年間にFIT設備の認定を取得しながら未だに未着工の太陽光発電等に対して、来年3月末を期限に同様の状態が続けば認定時の価格の引き下げ措置を行うとしたこと。いずれも根っこは、FIT制度開始後膨れ上がった賦課金(国民負担)の総額約2.4兆円を抑制するための対応である。
しかし、これら方針を決めるたった3ヵ月前に閣議決定した政府の「エネルギー基本計画」では、再生エネの主力電源化を打ち出し、2030~50年以降に向けた国際的な脱炭素化時代のベース的なエネルギー供給の主役を担うべきとしていた。計画では、化石燃料に代わる主力電源化を目指してさらなる量的拡大を図るとしながら、その一方で急激な価格抑制方策と買取価格減額を行うという、いわばアクセルと急ブレーキを同時に踏む政策展開が進められようとしている。かつて小泉純一郎政権時代の田中眞紀子外相(父は故田中角栄元首相)は、積極的な外交政策を展開しようとしたが、官邸からスカートの裾をいつの間にか踏まれ、前へ進もうにも進めないとぼやいたことがあったがその構図と似ている。
再生エネを中長期的にさらに一段と導入拡大しなければならないのは時代の要請であり、かつエネルギーセキュリティや化石燃料の輸入に莫大な国民の稼ぎを費やしている現実から見て論を待たないと言えよう。そこに急ブレーキをかければ、再生エネ事業者は右往左往するばかりで、これからの事業経営にも意欲をなくし、関連ビジネスからの撤退や廃業・倒産が増え、強いては再生エネ事業全体の衰退になりかねない。
経産省はアクセルとブレーキを同時に踏むのではなく、むしろ一定期間は推進のアクセル踏みつつ、現行の化石燃料資源の確保や原発などに偏重している財政支援のスキームを見直し、再生エネ事業の推進基盤整備こそに力を注ぐべきではないだろうか。
ノーベル賞、来年はペロブスカイト太陽電池に期待
2018/10/16(Tue) 文:(山)
今月初旬にノーベル賞の自然科学3賞が発表された。そのうち生理学・医学賞が京都大学高等研究員の本庶佑特別教授(76歳)らに授与されることが決まった。受賞理由は「免疫細胞制御分子の発見とがん治療への展開」。本庶さんはPD-1という免疫の働きにブレーキをかける分子を発見、がん細胞を攻撃する免疫の働きを活発にし、腫瘍の増殖や転移を抑えることに成功した。この研究が小野薬品工業のオプジーボ開発につながった。
残念ながら日本人の物理、化学賞の受賞者はなかった。でも来年以降の受賞が期待されている日本人研究者は少なくない。なかでもエネルギー関連で、有望視されているのが桐蔭横浜大学の宮坂力特任教授(65歳)である。宮坂さんは「効率的なエネルギー変換を達成するためのペロブスカイト材料の発見と応用」、つまりペロブスカイト材料が太陽電池に応用できることを見い出した。
ペロブスカイトは灰チタン石(CaTiO3)という鉱石で、これと同じ結晶構造をペロブスカイト構造と呼ぶ。宮坂さんは2009年に、この結晶構造が太陽電池に適していることを見い出し、実際に製作した。変換効率は当初3%台だったが、世界中の研究者が着目して研究が進み、10年足らずで20%台を実現し、シリコン太陽電池に近づきつつある。
材料費が安く製造プロセスがシンプルで、シリコン結晶に比べて低コスト、印刷のように基板に塗るだけなので、ビルや電車の窓、曲面のある車などにも塗布できる。このため、オフィスの節電や電気自動車などへの応用が期待される。課題だった耐久性も解決の突破口が見え、実用化へのハードルが下がった。最近ではインクジェット法によるペロブスカイト層の低温成膜に成功したと新聞で報じられている。一般的な樹脂基板の耐熱温度である150℃の条件で成膜し、インクジェット法では世界最高のエネルギー変換効率13.3%超を達成した。折り曲げ可能な太陽電池の実用化が視野に入ってきた。
今後、効率向上と長期間の耐久性維持が実現すれば、シリコン太陽電池にとってかわることも夢ではない。来年は地球温暖化の原因であるCO2を排出しない低コストの発電装置を開発した宮坂さんのノーベル賞受賞を期待したい。
パリ協定-日本は環境技術で存在感を
2018/10/02(Tue) 文:(一)
12月にポーランドで開かれる国連気候変動枠組み条約第24回締約国会議(COP24)が迫り、2020年以降の地球温暖化対策の新たな国際枠組み「パリ協定」のルールづくりが佳境を迎えている。15年末のCOP21で採択されたパリ協定は、翌16年11月に1年足らずで発効した。準備作業が追いつかず2年後のCOP24までに、検証や報告などの詳細な運用ルールを策定することが決められていた。
パリ協定は先進国に温室効果ガス排出削減を義務づけた京都議定書に代わる国際条約。各国が自主的に温室効果ガスの排出削減目標を策定し、5年ごとに見直して取り組みを徹底するスキームで、平均気温の上昇を産業革命前に比べ2℃未満に抑えるため、温室効果ガスの排出量を今世紀後半に実質ゼロとする目標を掲げる。
だが、採択時から総論賛成・各論反対の色彩が強かった。途上国はルールづくりに際して資金支援の増額を担保する仕組みを求め、長年にわたり先進国が大量の温室効果ガスを排出し続け、気候変動による海面上昇(高潮)などで生じた損失・被害への補償問題もくすぶる。9月上旬に草案作成のため、タイで事務方による最後の準備会合が開かれたが両者間の溝は埋まらず、具体的な中身はCOP24での政治決着に委ねられた。
日本は国際協力で環境技術・制度を移転するだけでなく、途上国との協働により新市場創出とライフスタイルの変革をもたらす「コ・イノベーション」を標榜する。経済成長していく途上国の温室効果ガス排出量を、いかに抑えるかが脱炭素社会実現のカギを握るのは確か。日本にとって国際協力を新たな経済成長に結びつける機会にもなる。環境省はこれまで推進してきた地熱発電に加え、各国の状況に合わせて廃棄物発電や熱電併給システム、洋上風力発電などの再生可能エネルギーを中心としたインフラ投資拡大を挙げる。
昨年、パリ協定からの離脱を表明したトランプ米大統領のパフォーマンスは相変わらずだが、国際社会は平静を保っている。“地獄の沙汰もカネ次第”ということわざはあるが、日本は環境技術で世界に存在感を示したい。
【これより古い今月のキーワード】 【今月のキーワード 最新版】