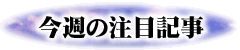地域の課題解決と脱炭素化を一体的に進める「脱炭素先行地域」の選定について、石原宏高環境相は2月13日の閣議後会見で、第7回目の地域として漁業振興を図る青森県中泊町や笠間焼で有名な茨城県笠間市など12エリア(4県14市町)を決定したと発表した。
今回の選定により2022年度から開始された地域選定は計102件(うち3件は辞退)となり、環境省は当初目標に掲げた「25年度までに少なくとも100ヵ所の地域選定」をほぼ実現したことから、一旦これで終了させ26年度以降に向けた新たな制度づくりを検討する。
地場産業振興・子育て・地域医療維持等多彩
「脱炭素先行地域」は、民生部門(家庭・業務など)における電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを2030年までに特定エリアで先行的に実現する制度。環境省の公募で選定されると、再エネ導入や断熱の省エネ事業などに最大50億円までの交付金が補助される。25年度の当初予算では約300億+GX関連85億、補正で335億円が計上された。
7回目となった今回の脱炭素先行地域には全国の自治体から18件の提案応募(非公表)があり、計12件(4県14市町)が新たに選定された(下記)。この結果、これまで選定された地域は北海道ブロックから九州・沖縄ブロックまでの計102件となって全国45道府県133市町村に拡がり、独自に関連施策を進める東京都などを除き、先行取り組みが進むことになる。
(以下については本誌№2860をご参照ください)
|