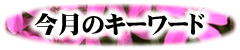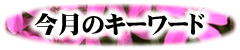熟練工が手を止める時、日本も止まる
2025/06/20(Fri)
文:(宗)
最近、テレビでヤマサキという会社のCMを見かけるようになった。高炉の耐火レンガを積み上げる築炉工が「炉が無いと鉄は生まれない。だから僕はその手を止めない」と言う内容で、鉄鋼業を支える職人を描いている。
製鉄の中心的存在でもある高炉は、20年程度で「巻替え」という大規模改修をしなければならない。高炉を輪切りにして分解し、内部の劣化した耐火レンガを剥がし、新しいレンガを一つ一つ積み上げていくという、地道な作業だ。多くの築炉工を動員して作業を進めていくのだが、レンガを緻密に積み上げる技能は一朝一夕で得られるものではない。それにも拘わらず一度巻替えが終わると、同じ高炉での次の仕事は20年も先。そのため各製鉄所で築炉工を抱えておくことは出来ない。従って築炉工は各製鉄所を回って順次仕事をこなすことになるが、それでも仕事の山谷が多く、熟練した築炉工の維持や育成は鉄鋼業にとって重要な課題だ。
その築炉工を将来的に維持できるかどうかは20年前から大きな問題だった。技術の習得には10年という時間と多くの工事経験を必要とするが、国内の高炉の数が減っていくなかで、複数の会社が巻替えで競合を続けると築炉工の維持・育成が出来なくなる。そのため以前は3社程度
が行っていた巻替え作業は、最終的に日鉄系に集約された経緯がある。しかし、築炉工の高齢化と典型的な「3K」の仕事で若い人が入ってこないことは長年の宿題となっていた。築炉工を確保することが出来なければ、高炉を動かし続けることはできない。「いつまで高炉操業を続けられるだろうか」という悲痛な声も聞こえてくる。
そういうこともあって、ヤマサキのCMを見てまずは築炉工をまだ維持できていることを確認できて安心した。このヤマサキという会社は、築炉工を維持していくため、高等学校卒業者を対象とした1年間の職業能力開発校を自社で運営している。これまで同社が築炉工を維持できたのは、こうした企業努力の賜物といえるだろう。
熟練工は製鉄だけではない。最新のガスタービンや原子力機器の製造や施工など、発電設備建設にも欠かせない。彼らが「その手を止めない」と言ってくれる間は良いが、担い手がいなくなった瞬間、日本の産業全体も止まるのだろうか。
トランプ外交と環境政策は「脱・マニュアル」で
2025/05/16(Fri)
文:(M)
「芽吹き始めた草木に、春の暖かい日が差し込む…」。出席した卒業式で聞いたあいさつの冒頭だ。
この日、東京は真冬に逆戻りした寒さで、雪が降っていた。祝辞で語られた情景と、積雪のある校庭の光景にギャップがありすぎて、心の中で失笑した。同時にあきれた。どうしても原稿をそのまま読まないといけないのか。大人なら雪の日の門出に触れる臨機応変さがあってほしかった。
融通のきかない様子を見て、作家の東野圭吾さんの「マニュアル警察」という作品を思い出した。推理小説家の著者にしては珍しい短編コメディーで、妻を殺した男が自首しようと警察署に出頭する場面から始まる。女性警察官に署で取り扱い中の事件かと聞かれ、男が「殺してきたばかり」と告げると、「事件の通報手続きをとって下さい」と窓口を案内される。
行った先の担当者から男は「第一発見者」扱いにされ、捜査員からは「奥さんが亡くなられました」「犯人への心当たりはないですか」と手順通りに声をかけられ、なかなか自首できない。
事件発覚前の自首がマニュアルにないためだ。
トランプ米大統領には、通常の外交マニュアルは通用しないだろう。常識外の高率の関税を課すと言い出し、発動した途端に停止する。赤沢亮正経済再生担当相が渡米すると、トランプ氏自らが交渉相手に名乗り出るなど展開が読めない。石破茂首相は「外交上のやりとりであり、言及を差し控える」とマニュアル通りに答弁したが、日本のリーダーとして国益を守る判断を下せるのだろうか。手腕が試される。
環境政策も既存のマニュアルは通用しない。気候変動が進行し、自然災害が多発しているからだ。海外では規制が強化されている。日本が例年通りに対策予算を執行して「現状維持」にできたと思っても、実際には「後退」している可能性もある。マニュアルがあると便利な面もあるが、頼りすぎると思考停止に陥り、必要な決断を遅らせることがある。卒業式のあいさつや小説のように笑い話で終わるなら良いが、外交も環境政策も手遅れになるとダメージが大きい。マニュアルに依存しすぎない臨機応変な判断を政治家や政府に期待したい。
東京ビッグサイト風景と我が国再エネ技術力
2025/02/28(Fri)
文:(水)
2月19 〜2 日に東京ビッグサイトで開催された「スマートエネルギーWeek( 春)2025」はさながら中国のどこかの会場ではないか、と錯覚するほど中国カラーに溢れた展示と取引商談が目についた。出展社数が約1600 社の会場は太陽光発電展(PVEXPO)、ゼロエミ火力発電展、
風力発電展、水素・燃料電池展などのゾーンに分かれていたが、圧倒的に中国系企業等のコマが多く、入場者もその団体・グループが多く見られ、中国語が盛んに飛び交っていた。それだけではなく、会場のスタッフにも若い中国女性が目立ち、戸惑いながら業務をこなしていた。
我が国はこの18日、脱炭素化社会づくりと再生可能エネルギーを主力電源とする「GX2040ビジョン」など3 国家戦略を閣議決定した。産業構造の改革とエネルギー自給率向上に直結する再エネ産業の自立化は待ったなしの課題としたものだが、主力の太陽光発電ビジネスでは機器導入の7 〜 8 割が中国製と言われており、国内関連企業は霞んでいる。
この展示会で目当てにしていた風力ゾーンの五洋建設コマに行ってみた。先月、同社は政府が導入拡大に最も力を入れている洋上風力の建設に不可欠な「大型基礎施工船」(HLV) の建造契約をシンガポールのSeatriumGroup等と契約したと発表。28年5月に完成させ、同年秋から
の稼働を予定する。芙蓉総合リースとの共同保有で、建造費は約1200 億円、電力ケーブルの敷設に必要な「大型作業船」(CLV) 建造費約310 億円を加えると、約1500 億円超の先行投資となる。
同社はZEB建設でも知られるが、洋上風力分野にも積極的でSEP船(風車据え付け船)を複数所有する。今回のHLV等建造は28 年以降本格化すると見られる浮体式の導入を見込み、15MW〜20MW級風車据え付けに必要なモノパイルが施工できる5000t 吊り全旋回クレーンを搭載するなど、自航式では世界最大級になるという。ただ、残念だったのはこの商談過程において、日本の造船メーカーは受注できない理由をさんざん示したが、契約したこのシンガポールの造船会社からは一発で「我々は十分にできます」との答えが返ってきたことだと、関係者は自嘲気味
に語っていた。
【これより古い今月のキーワード】